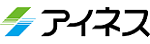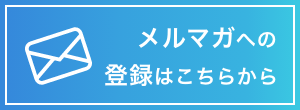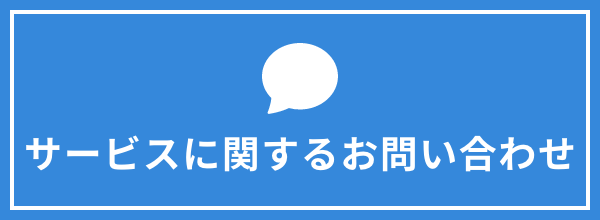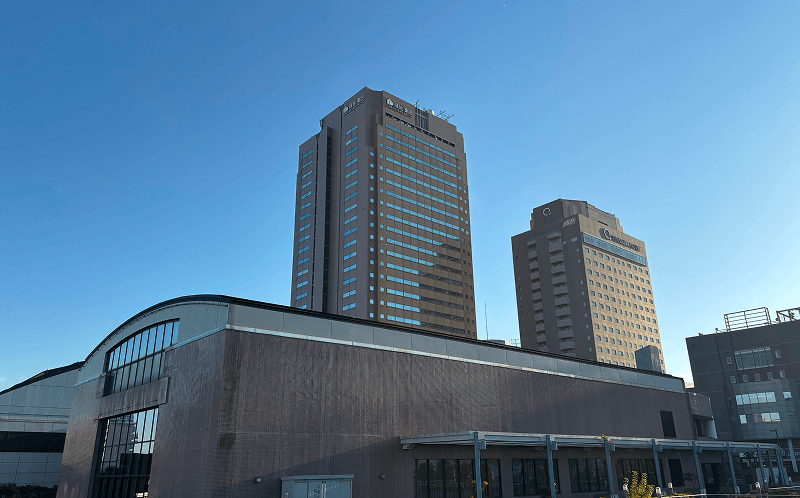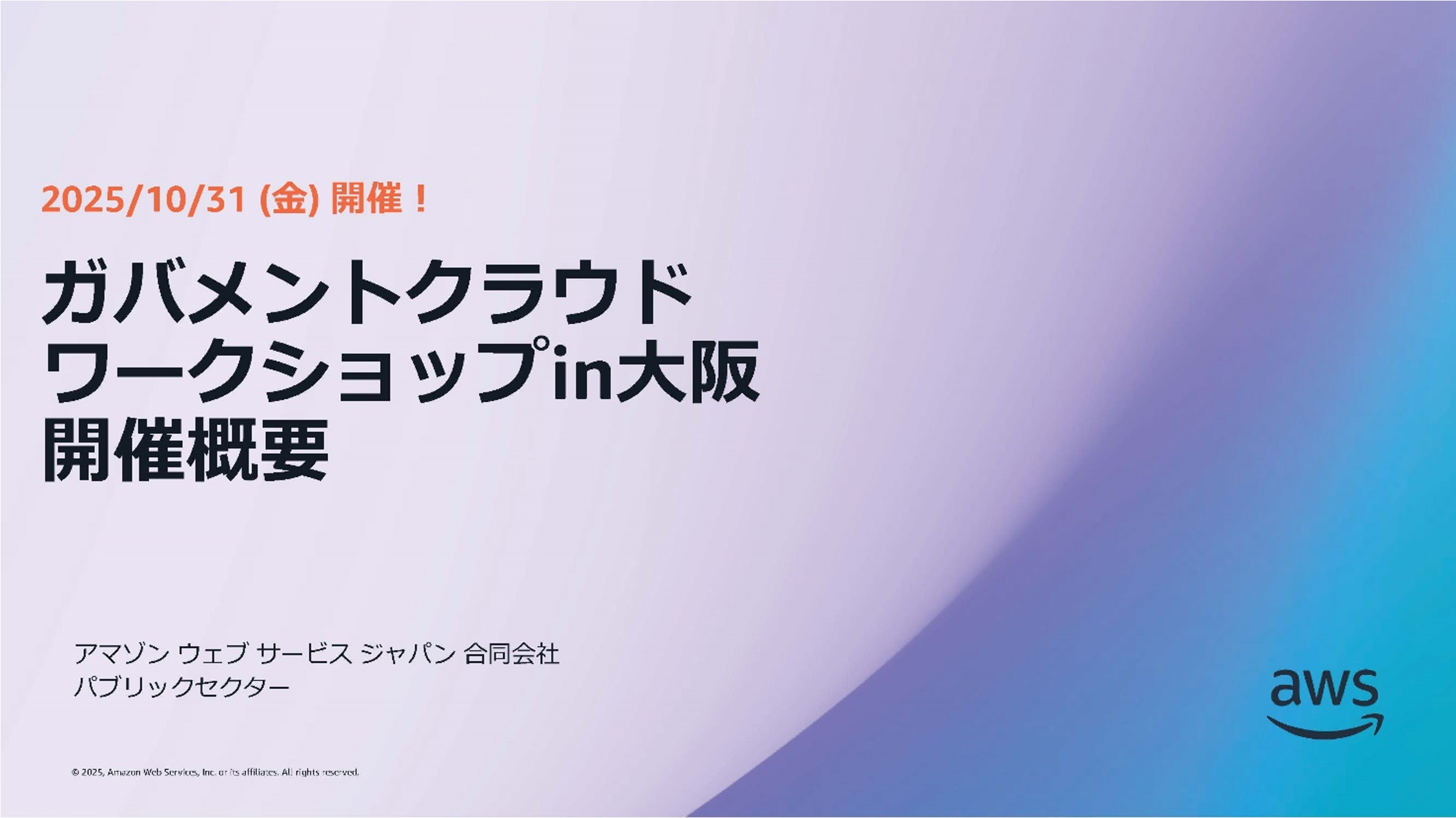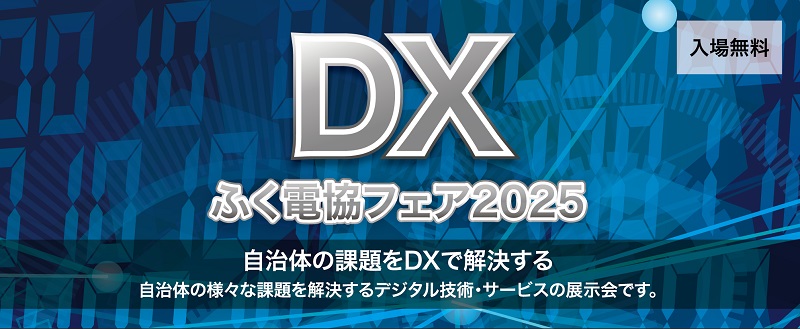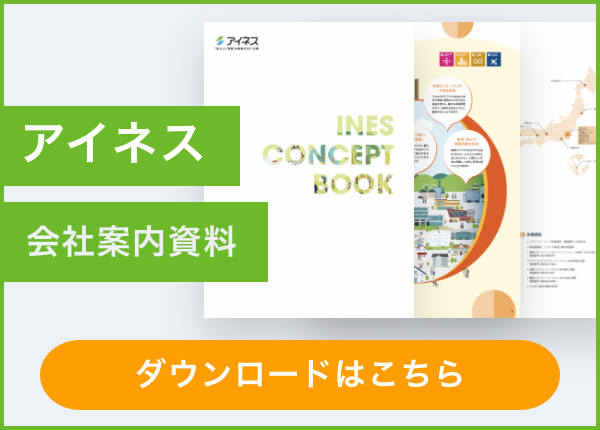- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- 改ざんは事実上不可能! 安全性の高い新技術「ブロックチェーン」とは
公開日
更新日
改ざんは事実上不可能! 安全性の高い新技術「ブロックチェーン」とは
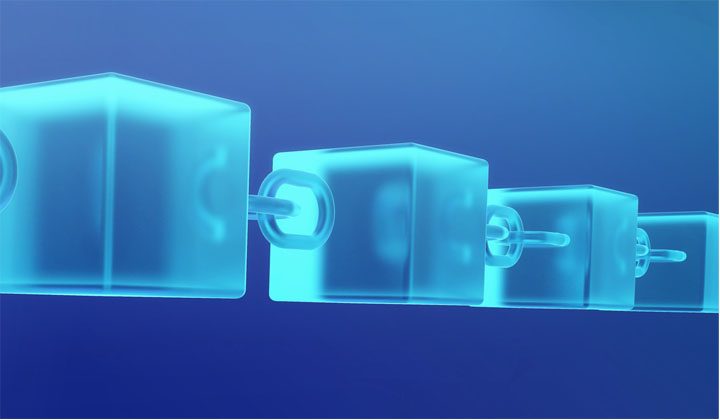
メディアなどで仮想通貨について取り上げられる機会が増え、「ビットコイン」をはじめ仮想通貨の認知度が上がるとともに世間に知れ渡るようになったのが、新技術“ブロックチェーン”です。ハッキングや改ざんがほぼ不可能であるという堅固な仕組みであることから、ビットコインだけでなく、ほかのフィンテックサービスや金融分野以外への応用が模索されています。
今回は、ブロックチェーンの仕組みとその特長、またブロックチェーンが抱える課題と今後の動向についてキーワードを用いながら簡単にご紹介します。
ブロックチェーンとは?ビットコインから見たその仕組みと特長
すべての記録が書かれたみんなで使える「台帳」
ブロックチェーンはもともと、ビットコインを仮想通貨として成り立たせるために、ナカモト・サトシという匿名の人物により開発された技術です。
簡単にいうと、およそ10分ごとに取引(トランザクション)の記録を集めて一つの塊(ブロック)にし、それらをチェーンのように時系列で順番につなげ、インターネット上のブロックチェーンネットワークの管理者たち(「マイナー」とよばれます。説明は後述。)のコンピューターに記録していくという仕組みです。
過去の全取引を記録したこの「台帳」はブロックチェーンに参加しているすべてのコンピューターで共有されています。
「台帳」自体は「Blockchain.info」で公開されていますが、具体的な取引内容はハッシュ関数(元となるデータからハッシュ値とよばれる不規則な文字列を生成する関数)により暗号化されています。
P2P方式
データは、ブロックチェーンネットワークの管理者たち(マイナー)のコンピューターで管理され、同じ情報が保存されます。
管理者たち(マイナー)が取引情報の整合性を確認し、50%以上の同意があればその情報が台帳に記入される仕組みです。
何者かが情報を改ざんしようとすると過去の台帳の全データを変更しなくてはならなくなるため、ブロックチェーンのデータ改ざんは実質的に不可能となるわけです。
また、複数の管理者(マイナー)によって管理されていることで、ある一か所のコンピューターが壊れたとしても影響はほとんどなく、システムダウンしにくい仕組みであるといえます。
このように、クライアントサーバー方式のような中央集権的なモデルとは対照的に、参加者同士が対等に通信し管理し合う方法を「P2P(ピアツーピア/Peer to Peer の略記)方式」といいます。
ブロックチェーンの機能を一言で表せば、「共通の台帳を分散管理する」ということになります。
プルーフオブワーク(PoW)
ブロックをチェーンのようにつなげる、と前述しましたが、ブロックを簡単に作れてしまってはデータの整合性が崩れたり改ざんされたりしてしまうので、ブロック生成には制約がかけられています。
取引記録のブロックをひとつ前のブロックにつなげるためには、決められた値(difficulty targetと呼ばれます)よりも小さなハッシュ値を求める必要があります。ブロックの中にあるnonceと呼ばれるエリアに書き込むデータを調整してブロックのハッシュ値を変化させ、決められた値よりも小さくなったら正しいブロックが完成する仕組みです。
条件を満たす値が見つかってブロックをつなごうとした時、すでにほかの人が新しいブロックをつないでしまっていたという状況もありえます。このように同じブロックに複数のブロックがつながれることをフォークと言います。フォークが発生した場合には、つながれたブロックが最も多いチェーンを有効とする決まりになっています。一番多くの仕事量をこなしたものを正規のものと認めるという考え方に基づいており、そこから「仕事量による証明」=「Proof of Work/プルーフ オブ ワーク」と名付けられています。これは不特定多数の参加者による合意形成方法(コンセンサスアルゴリズム)の一つと考えられています。
改ざんを行おうとすれば、他者を大幅に上回る計算速度をもってブロックチェーンを伸ばしていかなくてはならないわけですが、参加者全体の半数を上回る計算能力を持たない限りはほぼ不可能なため、ブロックチェーンの改ざんは事実上不可能と言われているのです。
マイナー(採掘者)
ハッシュ関数には解の公式が存在しないため解を求めるためには一つひとつ数字を入れ替えるような作業が必要であり、これをスピーディーに行うためには処理能力の高いコンピューターが必要となります。この計算を行うのが、ブロックチェーンネットワークの管理者たち(マイナー)です。
新しいブロックをつなぐことに成功した際には報酬としてビットコインが支払われますが、コンピューターリソースを提供してこの計算作業を行う管理者たちがマイナー(採掘者)と呼ばれる理由は、ビットコインの発行量が2,100万BTCとシステム的にあらかじめ決められており、有限である「金」と似せて発行量を埋蔵量と呼び、金が採掘されることに似せて、報酬としてビットコインが支払われることをマイニング(採掘)とよんでいるからです。
公開鍵暗号方式と電子署名
現在インターネットを介しての通信を暗号化する方式として使われているのが「共通鍵暗号方式」と「公開鍵暗号方式」です。この二者の違いは、暗号化および復号化するときに使う鍵が「共通鍵のみ」か「秘密鍵と共通鍵のペア」かという点です。
「共通暗号化方式」では、送りたい情報を暗号化して送るため万が一盗み見られてもそれだけでは問題ありませんが、複合化するための鍵も盗み見されてしまったら悪意のある人の手に秘密の情報が渡ってしまうことになります。
そこでこの問題を解決するために登場したのが「公開鍵暗号方式」で、暗号化と復号化の際に「公開鍵」と「秘密鍵」の二つが必要になります。
- 秘密鍵で暗号化したデータは、公開鍵でしか復号できない
- 公開鍵で暗号化したデータは、秘密鍵でしか復号できない
という仕組みになっているので、「秘密鍵」がなければ自分で暗号化したデータも復号できないことになります。「秘密鍵」は他人に絶対知られてはいけない「鍵」なのです。
この仕組みを活用して、「電子署名」の役割を持たせることもできます。
はじめに、「秘密鍵」を使ってデータを暗号化します。「公開鍵」を受け取った人がその暗号を復号化してデータを受け取ることができれば、その暗号化を行った人が「秘密鍵」の保有者であることの証明になることから「電子署名」と呼ばれているのです。
ビットコインでは、「電子署名」が使われています。
「公開鍵」を銀行口座のように考え、使用する際に「公開鍵」に相対する「秘密鍵」を持っている本人であると証明するのです。
ブロックチェーンが抱える課題と今後の動向
ブロックチェーンは、複数のコンピューターでデータを分散管理するという仕組み上、リアルタイムで同期することができず、およそ10分ごとに更新されます。そのため、株式売買のような処理速度を求められるような取引には向きません。
現在ビットコインのブロックサイズは上限が「1MB」に制限されていますが、新しいブロックが作られるのがおよそ10分に1回なので、処理できるトランザクション(取引)の数は限られてきます。今後ビットコインの利用者が増えていくと、処理されないトランザクションが滞留し、取引の遅延や、最悪の場合取引停止という事態も考えられます。 対応策としては、ブロックサイズを大きくしたり、補助役の別のブロックチェーンを導入したりといった策が考えられていますが、前述のとおりネット上にいるマイナーの合意がなければシステム変更できないのが現状です。これは、非中央集権的であることの弊害とも言えます。
また、今の仕組みはコンピューターを使ってひたすらハッシュ値を探すという単純なもので、非常に多くの電力を消費しておりエネルギー浪費とも考えられます。そのため、別の方法がないかと模索されているようです。
とはいえ、複数のコンピューター上でデータを管理している仕組みから、一つのデータが壊れたり改ざんされたりしてもほかのコンピューターから復元でき、改ざんやハッキングを受けにくい安全性の高い技術であることには変わりありません。
今後は、ビットコインをはじめとする仮想通貨にとどまらず、金融分野以外にもさまざまな分野でブロックチェーンが広まっていくと考えられます。すでに実現しているサービスとしては、たとえば「Soul Gem」というアプリがあります。これは、ブロックチェーンの「改ざんされず永久に残る」という特性を利用して「愛の証明」を行うというもので、結婚証明書や恋愛証明書を発行してもらうことができます。
一方ビジネスの場面では、ブロックチェーンの特性を生かして、法人同士の契約に関するシステムや、医療機関ごとに分散しないで個人の一貫した記録が残せる医療カルテシステム、食品などのトレーサビリティや著作権システムなどの実現が期待されています。 実際、米国のデラウェア州では法人登記を、ホンジュラスやグルジアなどでは土地登記をブロックチェーン上で行うことが検討されています
ブロックチェーンがさまざまなところで活用されるようになれば、私たちの仕事や習慣の概念が変わるかもしれません。私たちの生活にどのように入り込み、存在感を示していくのか今後の動向に注目したいと思います。
※記載されている会社名・商品名・サービス名等は、各社の商標または登録商標です。
関連記事