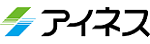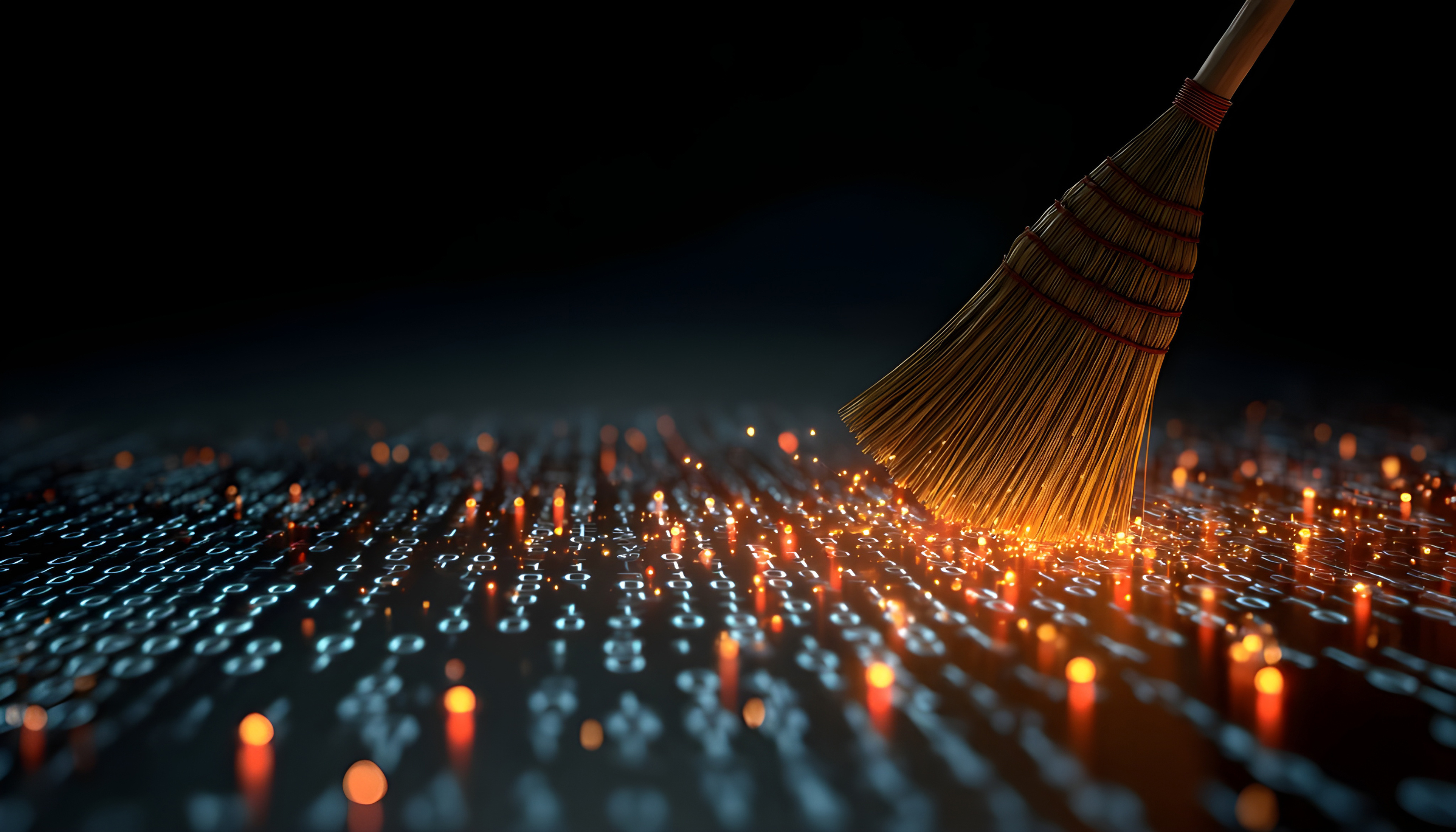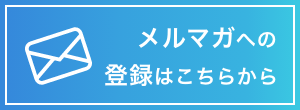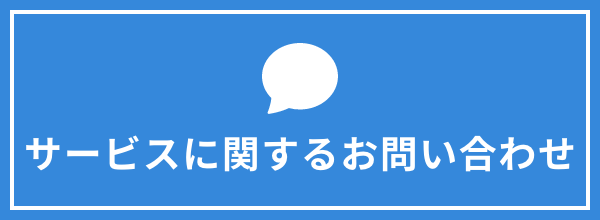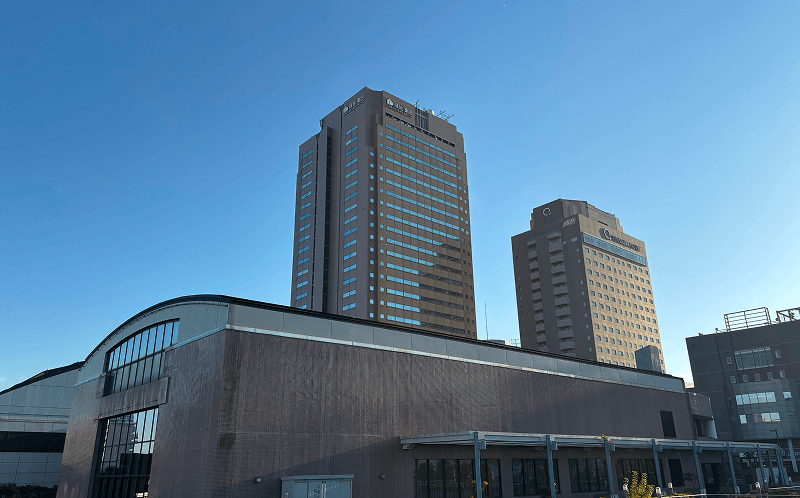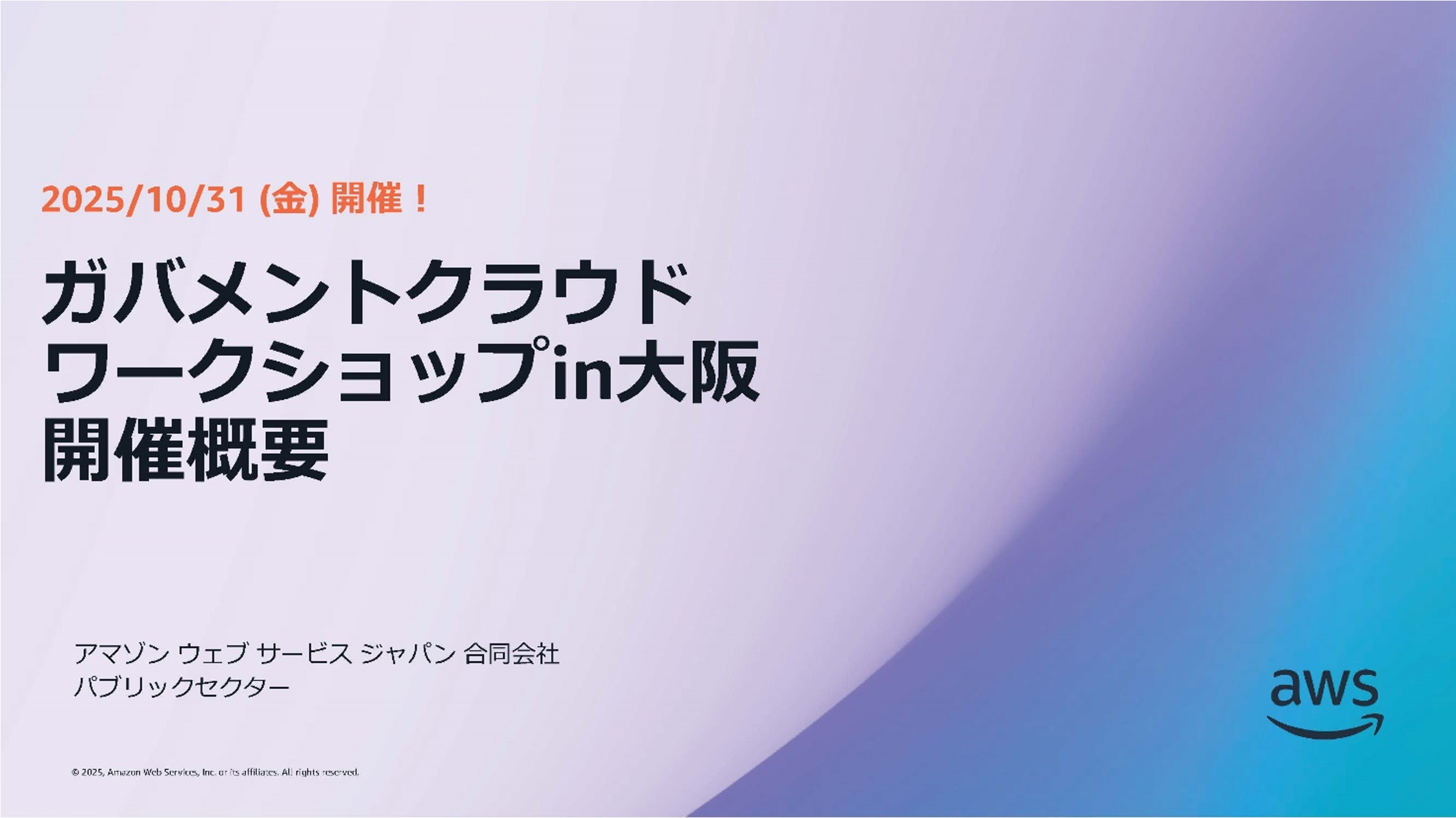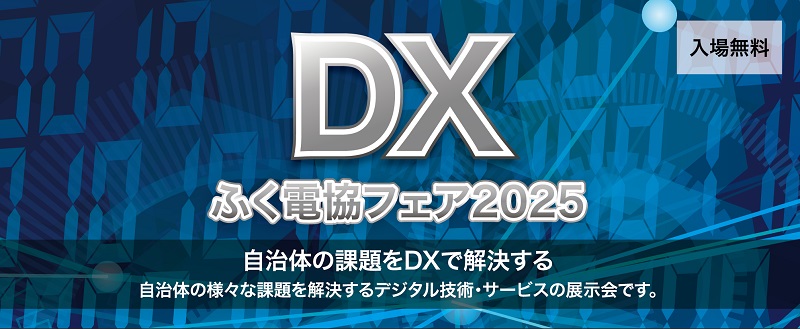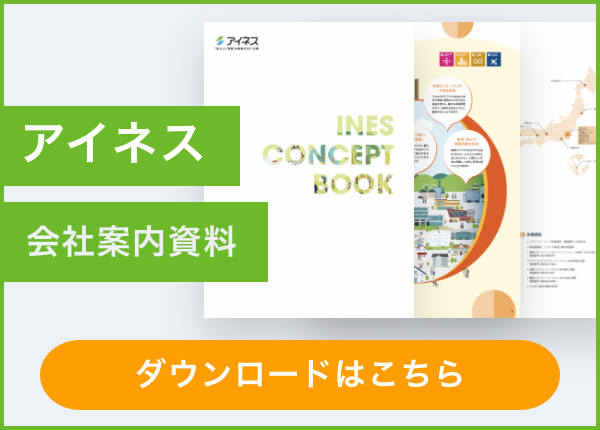- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- 自治体におけるAIの導入状況や導入メリットを解説
公開日
更新日
自治体におけるAIの導入状況や導入メリットを解説
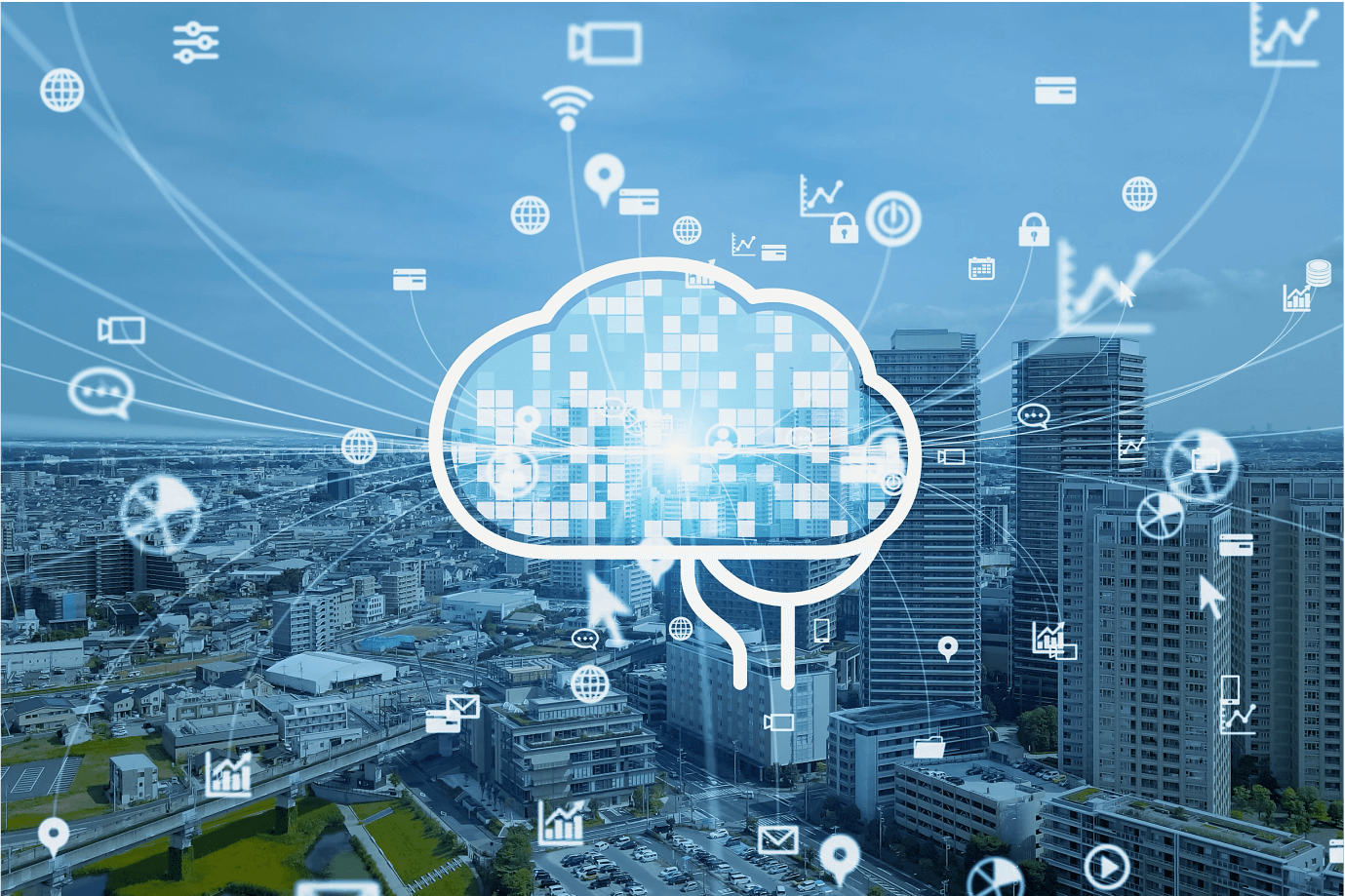
業務にAIを導入している自治体は年々増加しています。これは、AI導入が職員の業務負荷軽減やコスト削減、行政サービスの品質向上などさまざまなメリットをもたらすためです。
ただ、AIの導入には専門知識を持つ人材や導入コストを確保する必要があります。また、正しい活用方法を理解しておかないと、情報漏えいや著作権侵害などのリスクがある点にも注意が必要です。
そこで本記事では、自治体におけるAIの導入状況や導入メリット、AIを導入するうえでの注意点などを解説します。実際にAIを導入した自治体や導入効果の事例も紹介するので、AI導入を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
7.まとめ
自治体におけるAIの導入状況
近年進化が目覚ましいAI技術は、企業だけでなく自治体でも導入するところが増えてきています。
総務省が公開している「自治体におけるAI・RPA活用促進」によると、AIやRPA(ソフトウェアロボットによる業務自動化)を導入済みの自治体は、令和3年度時点で都道府県単位では100%に到達しています。政令指定都市の導入率は、令和3年時点で100%です。
政令指定都市以外の市区町村においてもAI・RPAの導入率は年々上昇しており、令和5年度時点では50%に達しています。数年後には、すべての市区町村がAI・RPAを業務に活用するようになるといえるでしょう。
<AI・RPA導入済みの自治体の比率>
| 年度 | 都道府県 | 政令指定都市 | その他市区町村 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 36% | 60% | 4% |
| 令和1年度 | 68% | 50% | 8% |
| 令和2年度 | 85% | 80% | 21% |
| 令和3年度 | 100% | 100% | 35% |
| 令和4年度 | 100% | 100% | 45% |
| 令和5年度 | 100% | 100% | 50% |
地方自治体が導入しているAIの機能にはさまざまなものがあります。総務省「自治体におけるAI・RPA活用促進」を参考に機能別に分類すると、導入されている主な機能は以下のとおりです。
| 機能 | 用途 |
|---|---|
| チャットボット | ・住⺠問い合わせ対応 ・庁内ヘルプデスク対応 ・観光情報提供 |
| 音声認識 | ・会議事録作成 ・多言語翻訳 |
| 文字認識 | ・申請書読取 ・調査票読込 ・アンケート読込 |
| マッチング | ・保育所入所マッチング |
| 画像・動画認識 | ・道路損傷検出 ・固定資産(住宅)調査 ・歩行者/自転車通行料の自動計測 |
| 最適解表示 | ・国保特定健診の受診勧奨 ・国民健康保険レセプト内容点検 ・戸籍業務における知識支援 ・乗合タクシーの経路最適化 |
| 数値予測 | ・次年度予算額の最適値推定 ・観光客入込状況の予測 |
総務省「自治体におけるAI・RPA活用促進」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf
自治体でAIの導入が増えている背景
自治体でAIの導入が増えている背景には、人手不足が大きく影響しています。年齢別の地方公務員数を見ると、大きな割合を占めているのは団塊ジュニア世代です。2040年頃には団塊ジュニア世代が65歳以上を迎え、職員数は大幅に減少することがわかっています。
我が国の内政上の危機を乗り越えるための施策を検討する「自治体戦略2040構想研究会」においても「より少ない職員で効率的に事務を処理する体制の構築が欠かせない」としており、その施策として注目されているのがAI技術です。
近年は、ChatGPTの登場をきっかけにAI技術はより身近なものになってきました。業務を効率化できるAIツールも次々にリリースされています。今後、自治体におけるAIの導入は加速度的に増えていくと予想できるでしょう。
自治体がAIを導入するメリット
自治体におけるAI導入には、さまざまなメリットがあります。主なメリットは、以下の6点です。
・文書や書類を作成する業務の効率化
・窓口対応業務の効率化
・その他さまざまな業務の効率化
・コスト削減
・サービスの品質向上
・行政の透明化
文書や書類を作成する業務の効率化
自治体業務において多くの工数がかかる文書・書類作成の業務は、AIの導入によって大幅に効率化できます。議会答弁の記録や議事録をはじめ、文書・書類作成は自治体業務において多くの時間と労力を必要とする業務です。
例えば、ChatGPTのような生成AIは、これまでの文書・書類のデータを元に学習させることで、必要な文書を自動生成可能です。一部の文章の作成を生成AIに任せれば、業務を効率化できます。同じ生成AIを使って、フォーマットや表現を統一できるのも利点です。
また、AIを活用した文字起こしツールを使えば、議事録の作成も容易になります。時間がかかる音声データのテキスト化や、議事録の要約はツールが行ってくれるため、資料作成にかかる人件費や時間を大幅に削減できるでしょう。
作成した文章の校正にもAIが活用できます。手作業でのチェックや調整の必要性は残るものの、ミスの発生率を下げられるでしょう。業務の効率化だけでなく、文書の品質アップが期待できるのもAI導入のメリットのひとつです。
窓口対応業務の効率化
窓口での問い合わせ対応や手続きといった業務も、AIの導入によって効率化が期待できます。
例えば生成AIを活用したチャットボットは、住民からの問い合わせの効率化に有効です。チャットボットなら問い合わせに即座に対応でき、疑問点の解消や必要な手続きへの誘導ができます。職員窓口とは違って24時間対応できるのもチャットボットの大きな利点です。
AIによる音声認識技術も、窓口業務を効率化します。従来の問い合わせフォームはテキスト入力が必要なので、一部の高齢者などには使いにくいものでした。AIの音声認識技術により音声での手続きが可能となるため、テキスト入力が難しい住民への対応も効率化できます。
多言語翻訳技術を使えば、外国人への対応も効率化可能です。対応スピードを上げることで窓口の混雑を緩和できるほか、これまで外国語が扱える職員に集中していた負荷の分散にもつながるでしょう。
その他さまざまな業務の効率化
ほかにもAI導入によってさまざまな業務が効率化されています。例えば、AIのマッチング機能を使えば、保育所への入所を希望する世帯と保育所をつなぐ業務を効率化可能です。
ほかには、画像・動画認識機能の活用で、道路の損傷検出や歩行者・自転車通行量の自動計測が可能となります。手作業と比べると作業に割く人員数が大幅に削減できるだけでなく、検出・計測の精度が向上するのも大きなメリットです。
数値予測もAIが得意とする作業のひとつです。予算額の推定や観光客数予測など専門的な知識を必要とする数値予測作業も、AIを導入することで容易かつ正確に実施することができるようになります。
コスト削減
上記のような文書・書類作成の効率化や、窓口業務の効率化により人件費をはじめとしたコスト削減が可能です。AIは、これまで職員がかけていた工数の多くを肩代わりしてくれるため、より少ない職員で対応できるようになり、残業時間などの短縮も期待できます。
また、AI導入に付随して、一部の業務がペーパーレス化されるのもポイントです。人件費と比べるとインパクトは小さいものの、紙コストの削減も期待できるでしょう。
AI導入には初期費用や運用コストがかかりますが、人件費・紙コストの削減を考慮すると、中長期的にはコストダウンにつながるといえます。
サービスの品質向上
AIの導入がもたらすのは、業務の効率化やコスト削減だけではありません。行政サービスを利用する住民にとっても、質の高いサービスを受けられるようになるのは大きなメリットだといえます。
代表的なサービスの品質向上は、受付時間の拡大です。前述の生成AIを活用したチャットボットは、職員窓口とは違い24時間365日住民からの問い合わせに対応できます。普段、窓口の受付時間に間に合わない人への対応はもちろん、災害発生時にも即座に対応可能です。
また、文字を認識できるAIを活用すれば、手続きのスピードアップも見込めます。職員の工数削減はもちろんのこと、手続き完了までの待ち時間を短縮できるのもメリットです。
行政の透明化
住民にわかりやすい資料を公開できるのもAI導入の利点です。例えば、議会の議事録などは、手作業よりもAIツールを使った方が効率的かつ見やすくまとめられます。従来よりもわかりやすい議事録を、よりスピーディに公開できるでしょう。
そのほかの行政データも、AIを使えば分析・可視化が容易です。複雑でわかりづらいことが原因で住民に見てもらえなかった情報も、AIによってわかりやすくアレンジすれば多くの人に届くでしょう。結果的に、住民からの信頼感につながります。
自治体におけるAI導入の課題と対策
AIの導入が自治体の業務効率化やサービス向上に貢献する一方で、導入にはいくつかの課題が存在します。
ここでは、自治体がAIを活用する上で直面する主な課題と、それに対する具体的な対策について解説します。
AIを活用するための人材不足
自治体でAIを効果的に活用するためには、適切な知識を持つ人材が必要です。
しかし、多くの自治体では、AIを活用できる職員が不足しており、既存の業務と並行してAI導入に取り組むことが難しいのが現状です。
特に、AIモデルの選定、データの収集・管理、システム運用に関する専門知識を持つ職員が少なく、外部のベンダーに頼るケースが多くなっています。
対策としては、次の3点が考えられます。
- ・職員のAIリテラシー向上
- ・専門人材の採用・育成
- ・外部パートナーとの連携
予算確保の難しさ
AIの導入には、システムの開発・運用コストが発生します。特に、AIをカスタマイズして自治体のニーズに最適化するには、多額の予算が必要となります。
しかし、地方自治体では財政的な制約があり、AI導入のための予算確保が難しい状況が続いています。
対策としては、次の3点が考えられます。
- ・クラウド型AIサービスの利用
- ・国や自治体の補助金・助成金の活用
- ・ほかの自治体との共同導入
データのセキュリティとプライバシー
AIを活用するためには大量のデータを取り扱う必要がありますが、その過程で個人情報や機密情報が関与するケースが多いため、セキュリティ対策が不可欠です。
特に、住民データをAIに活用する場合、データの管理が不適切だと情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まります。
対策としては、次の3点が考えられます。
- ・プライバシーポリシーの策定と透明性の確保
- ・適切なデータ管理体制の構築
- ・外部専門機関の監査を受ける
導入後の運用と持続可能性
AIは導入して終わりではなく、継続的な運用が求められます。
しかし、多くの自治体では、導入後の運用体制が整っておらず、AIが十分に活用されないケースも発生しています。
また、技術の進化に対応できる体制を構築しなければ、導入したAIの効果が薄れる可能性があります。
対策としては、次の3点が考えられます。
- ・運用マニュアルの作成
- ・長期的な運用計画の策定
- ・定期的な評価と改善
自治体におけるAIの導入事例
ここでは、実際にAIを導入した自治体の事例を、総務省で公開されているものなどから3つご紹介します。
保育所入所選考業務へのAI導入事例(埼玉県さいたま市)
埼玉県さいたま市は、保育所入所選考業務の効率化と結果通知の早期化を目的として、AIのマッチング機能を導入しました。AIが行うのは、入所申込情報を読み取り、入所希望順位・兄弟などの条件を考慮して振り分ける業務です。
AIを導入した結果、職員が1,500時間かけていた入所選考作業が、マッチング機能を使うことにより、数秒で完了しました[注1]。選考結果の通知も従来より1週間程度前倒しが可能となり、結果を受けて保護者は復職などの検討時間を確保できます。
この取り組みはほかの自治体にも展開され、東京都や大阪府でも作業時間の短縮や通知の早期化を実現しました。
[注1]総務省「AIによる保育所入所選考マッチング」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000683248.pdf
⾳声書き起こしソフトによる会議録作成支援(愛知県東郷市)
愛知県東郷市は、各科主催の会議などに音声書き起こしソフトを使用し、業務の効率化を図りました。ソフトの精度を確認するために庁内の複数の会議で使用し、方言の登録や指向性マイクの導入など、効果的な使用方法も検討しています。
ソフトの導入により、従来数時間かかっていた作業が数分で完了しました。職員の事務負荷を軽減できたと報告しています。
ほかの自治体への展開事例では、外部委託していた書き起こし作業が委託なしで行えるようになり、時間も12週間から5週間に短縮できたものもあります[注2]。委託料などのコスト削減も報告されているメリットのひとつです。
[注2]総務省「AIによる⾳声データのテキストデータ化」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000683248.pdf
市民からの相談業務で生成AIを活用し、相談記録票の作成時間を短縮(神奈川県横須賀市)
横須賀市では、市民がどこへ相談すれば良いか判断のつかない福祉相談を受ける総合窓口「ほっとかん」を、令和2(2020)年4月よりオープン。市民からの相談を受け付け、担当課へ迅速につなげています。
しかし、相談業務に対応する職員の経験の長さによって対応の質に差が出てしまうこと、相談記録票を作成するのが17時以降の残業時間になってしまうことなどが課題となっていました。
そこで、アイネスの「AI相談パートナー」を導入したところ、相談記録票の作成業務において効率化を図ることができ、市民と向き合える時間が増え、担当課への引き継ぎもスムーズになりました。
[注3]【神奈川県横須賀市様】「AI相談パートナー」の生成AI活用で、相談記録票の作成時間を短縮し、市民からの相談業務の効率化を実現
https://www.ines-solutions.com/case_study/yokosuka-kanagawa
生成AIの要約機能を活用して市民からの相談業務の負担を心理的にも時間的にも軽減(新潟県長岡市)
新潟県長岡市では、年間約1,500件にものぼる市民からの健康相談業務に保健師15名が対応していました。しかし、相談を受ける業務に付随する相談記録票の作成などに時間を取られ、過大な業務負担の改善が課題となっていました。
そこで、アイネスの「AI相談パートナー」を導入。導入前は、電話を取りながら手書きでメモを取り、後でメモを見返しながら記録票を作成していたところから、メモを取らなくても記録が残るので、安心してより相談に集中できるように。
さらに、要約機能の活用により、相談業務を大幅に効率化し、相談業務の心理的、時間的負担を大きく軽減できました。
[注4]【新潟県長岡市様】生成AIの要約機能がついた「AI相談パートナー」で、相談業務の負担を心理的にも時間的にも軽減
https://www.ines-solutions.com/case_study/nagaoka
自治体がAIを活用する際の注意点
自治体がAIを活用する際には、いくつかの注意点があります。主に以下の4点には注意が必要です。
・AI導入に取り組むための人材と知識が必要
・セキュリティ対策が必要
・予算の確保が必要
・導入後の運用が重要
AI導入に取り組むための人材と知識が必要
自治体がAIを導入するためには、必要な知識・スキルを持つ人材の確保が必要不可欠です。現状、AIを導入できていない自治体の多くは、この人材確保に課題があると考えられています。
AI導入を検討・推進する人材が不足する場合は、外部の専門家との連携も有効です。AI導入済みの自治体も増えているため、自治体にAIを導入した実績のある業者も多く存在します。ほかの自治体などにも協力を仰ぎながら、不足している知識・スキルを補いましょう。
セキュリティ対策が必要
生成AIの活用には、情報漏えいや著作権侵害のリスクがつきまといます。例えば、機密情報や個人情報をAIに学習させると、情報漏えいのリスクがあるため注意が必要です。また、生成AIが作成したコンテンツについても、必ずしも著作権侵害をしていないとは限りません。
何かと便利なAIですが、安全に活用するためには使用上のルールをまとめたガイドラインの策定や、徹底した情報管理の体制構築が必要です。職員への教育はもちろん、AIが生成した文書・コンテンツなどは必ず人の目でチェックするようにしましょう。
予算の確保が必要
AIの導入には初期費用や利用料金がかかるため、予算の確保が必要です。AI技術そのもののコストだけでなく、使用するための機材やシステム開発にもコストが発生する点には注意しましょう。予算確保の難しさも、AI導入が進まない自治体が抱える課題のひとつです。
予算を確保するには、AI導入によるメリットを大きくアピールする必要があります。工数削減による効率化やコスト削減、サービスの品質向上などの効果を予測し、自治体の長や地域住民の理解を得られるようにアピールしましょう。
導入後の運用が重要
AIはただ導入するだけでなく、導入後の適切な運用が重要です。便利なツールを導入しても職員が効果を実感できなければ、最大限のメリットを発揮できたとはいえません。使用上のルールやマニュアルを作成し、日常的に使用者をサポートしていく必要があります。
また、AIが完全ではないことを理解しておくことも大切です。AIが学習データとは異なる誤った情報を生成する「ハルシネーション」という現象をはじめ、AIにも間違える可能性があることは知っておきましょう。
したがって、AIが生成した情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、人の目によるチェックが必要不可欠です。また、AIが誤った情報を生成した際の対処法を整備しておくことも重要だといえます。
まとめ
本記事では、自治体におけるAI導入の現状やメリット、注意点について解説しました。自治体業務にAIを導入すれば、職員の業務負荷軽減やコスト削減、行政サービスの品質向上などさまざまなメリットが見込めます。
令和5年度時点ではすべての都道府県・政令指定都市がAIを導入しており、その他の市区町村においてもAI導入率は50%に到達しています。今後も、自治体におけるAI導入率は、年々上昇していくと考えられるでしょう。
自治体業務にAIを導入する際は専門知識・スキルを持つ人材や導入コストを確保する必要があります。また、AIは導入して終わりではなく、ガイドラインやマニュアルを整備して正しく運用する必要がある点にも留意が必要です。
なおアイネスでは、AIを活用した自治体相談業務支援サービス「AI相談パートナー」を通して、自治体における相談業務の効率化を支援しています。
AI相談パートナーのサービス機能
会話の自動テキスト化(文字起こし)機能
AI音声認識技術を用いて、会話内容をリアルタイムに自動でテキスト化(文字起こし)します。テキスト化した内容は保存できるので、相談記録票を作成する時に活用でき、そのまま関係者に共有可能です。
職員支援ガイダンス表示機能
相談対応中の会話内容に応じて、相談対応に役立つガイダンスを表示します。ガイダンス内容は、深堀してヒアリングすべき項目、関連行政サービス情報、関連法案等です。
記録票作成サポート機能
テキスト化された会話内容に対し、個人が特定される恐れのある情報を自動でマスキングします。
相談業務で必要とされる観点要約により、相談員の業務負荷を圧倒的に削減します。
AI相談パートナーは、低コストでのスモールスタートも可能です。各種AI技術の導入を検討している自治体関係者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【お問い合せ先】
今回、ご紹介しましたアイネスの「AI相談パートナー」について、より詳しい内容をお知りになりたい方は、下記からお問い合わせください。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。 弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。
ITでお悩みのご担当者様へ

関連記事