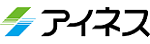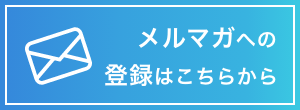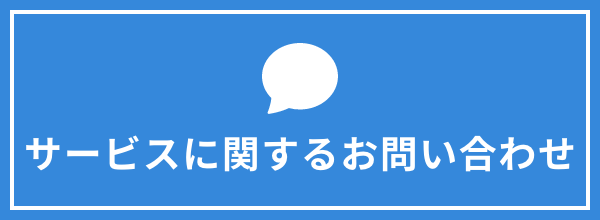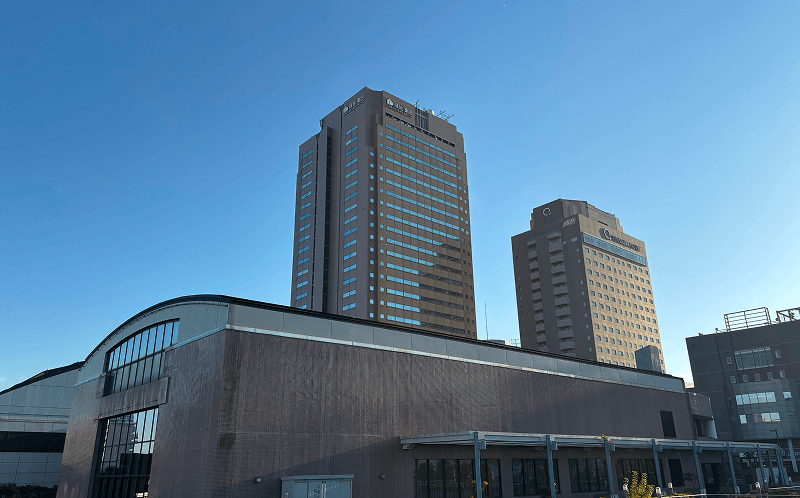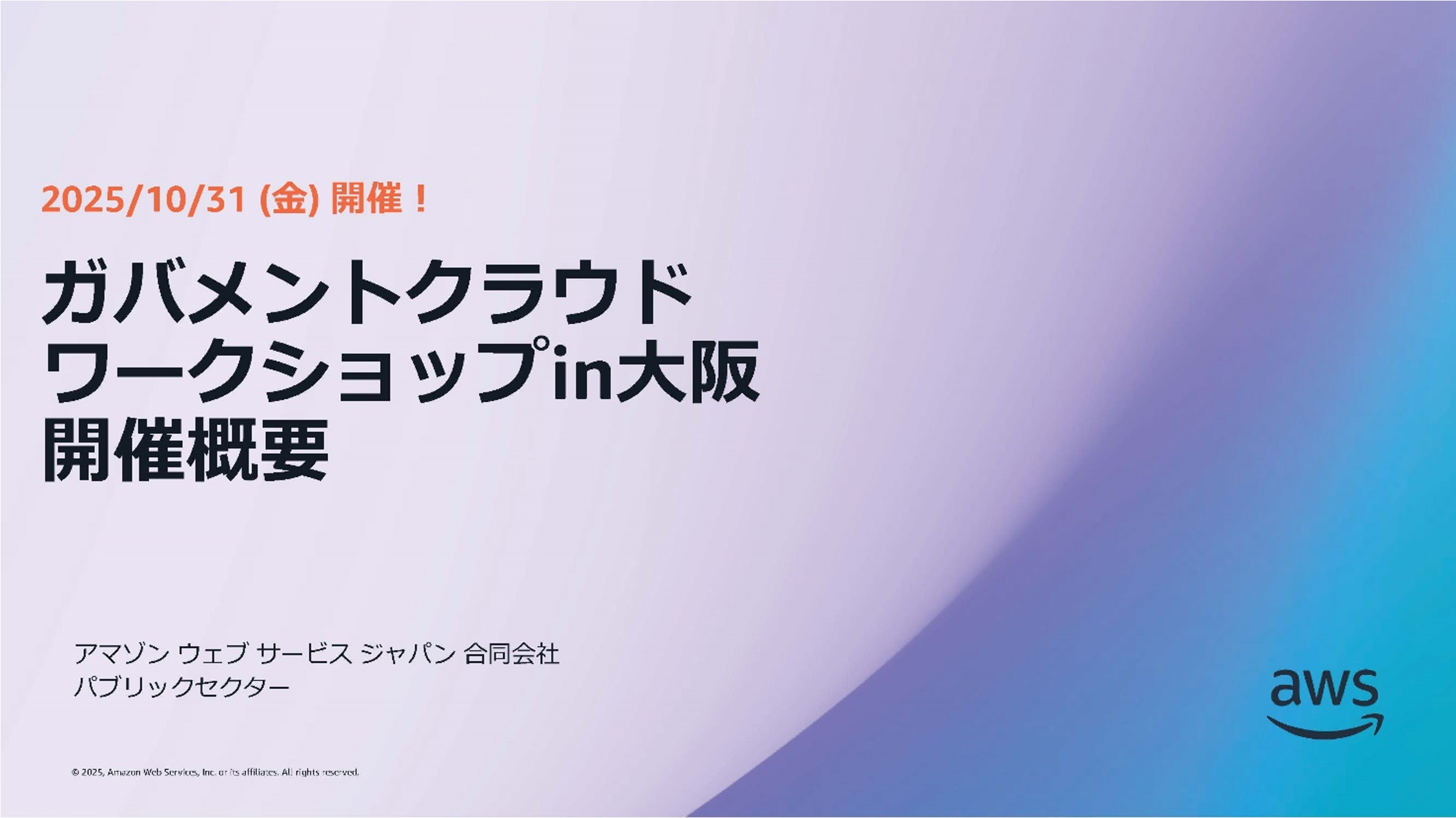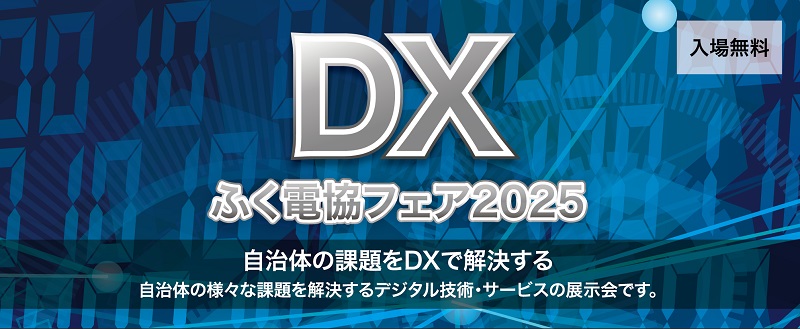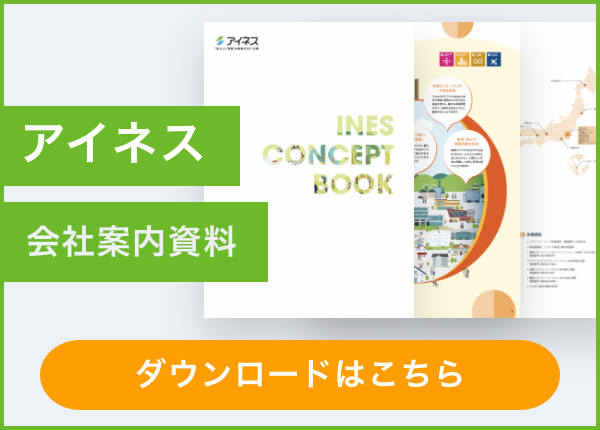- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- 食品ロス問題とは?小売業者もデータ分析で貢献できる!
公開日
更新日
食品ロス問題とは?小売業者もデータ分析で貢献できる!

世界の人口のうち、約10%が慢性的な栄養不足にあります。しかし、現状の世界の穀物生産量や在庫量から、食料の量は十分にあるといわれており、先進国における食べ残しや賞味期限切れなどによる廃棄と、開発途上国における技術不足などによる廃棄が問題視されています。いわゆる「食品ロス問題」です。
食品ロスは、環境へ負荷をかける点も問題で、食品を生産するためにかかった資源も無駄になってしまいます。
本コラムでは、日本における食品ロス問題についての現状と原因、食品を取り扱う小売業者様が解決のためにできることについてご紹介いたします。
参考:「世界の食料安全保障と栄養の現状(2021年報告)」国連食糧農業機関
食品ロス問題とは?
改めて、食品ロス問題とは、本来であれば食べられるはずの食品が捨てられてしまっている問題です。国連食糧農業機関(FAO)が2011年発表した「世界の食料ロスと食料廃棄」によれば、世界では毎年、生産されている食料の3分の1(13億トン)が廃棄されているといいます。
先進国と開発途上国の食品ロス問題の違い
冒頭でもお伝えしたように、食品ロス問題の原因は先進国と開発途上国とで異なります。
日本をはじめ、先進国では食品が十分に行き渡っており、消費段階で賞味期限切れや食べ残しといった理由で廃棄されています。
一方、開発途上国では、生産段階・流通段階で、大量に収穫できた農作物を適切に保管できなかったり、十分な加工技術がなかったり、輸送のための費用が捻出できなかったりといった理由で廃棄されています。
「食品ロス問題」は、何が問題なのか?
食品ロス問題には、2つの側面があります。
一つは、世界人口の1割が飢餓に苦しんでおり、慢性的な栄養不足を抱えているにも関わらず、食品が無駄になり廃棄されているという矛盾です。本来であれば、世界人口に食料が行き渡るだけの十分な量が生産・備蓄されているのです。
SDGs(持続可能な開発目標)では、2030年までに飢餓をゼロにすることを掲げています。目標達成のためにも、廃棄されている食品を無駄にすることなく消費する方法を模索する必要があります。
もう一つは、環境への負荷の問題です。食料を廃棄するために行われる焼却によってCO2をはじめとする温室効果ガスが排出され、地球温暖化が進んでしまうのです。
また、生産のために使った資源が無駄になる点も問題です。食料となる穀物や野菜、動物などを生産する過程で、水や農地、エネルギーなど多くの資源を利用していますが、廃棄すればこれらはすべて無駄になってしまいます。
日本における食品ロス問題の現状
上記のように、食品ロス問題は先進国と開発途上国とで抱える課題がそれぞれ異なります。
特に日本では、食品ロスは発生源別に「事業系」と「家庭系」に分けることができます。
事業系の食品ロスとは?
事業系の食品ロスとは、メーカーや流通業者、外食産業など、食品関連の事業者から排出される廃棄物に由来する食品ロスです。
たとえば、生産過程の品質管理で規格外となり流通されなかった食品や、飲食店で来客が食べ残した料理、小売店で仕入れたクリスマスケーキなど季節ものの商品がシーズンを過ぎた際の廃棄、在庫の賞味期限切れ商品の廃棄などが該当します。
家庭系の食品ロスとは?
家庭系の食品ロスとは、一般消費者の家庭で生じる食品ロスです。
たとえば、作り過ぎ、買い過ぎによって消費し切る前に消費期限が過ぎたり腐敗したりして廃棄するケースなどが該当します。
農林水産省のWebサイトによれば、日本では全食品資源の5~10%が食品ロスとなっていると推計されています。事業系の食品ロスと家庭系の食品ロスとが半々で、それぞれ1,100万トンとなっています。
参考:「食品ロスの現状を知る」農林水産省
日本は先進国の一つですが、高齢者やひとり親世帯など、貧困ライン以下で生活する人が16.0%(2,000万人以上)もいると推計されています。近隣の小売店などに食品があっても、お金がなくて購入できずに食べられない人がいる一方で、食べられるはずだった食品が廃棄されているというのが日本の食品をめぐる現状なのです。
廃棄のためには金銭コストもかかります。食品を扱う企業にとって食品ロス問題は、SDGsや地球環境のためだけでなく、健全な経営のためにも取り組む必要のある課題といえます。
日本の食品ロス問題が深刻化した原因
上でご紹介した事業系の食品ロスについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
日本の事業系食品ロスで廃棄が多いのは「食品製造業」
環境省のWebサイトによれば、日本の事業系食品ロスのうち、最も廃棄量が多いのが食品製造業で、令和2(2020)年度で121万トン。生産段階では、規格外の商品や欠品対策のための余剰生産分などが廃棄されています。
一方、食品小売業については、60万トンと食品製造業の約半分。廃棄理由は、売れ残りや破損のほか、季節商品・定番商品の入れ替えとなっており、一般的に生鮮食品の売れ残りが占める割合が高いといわれています。
「2021年スーパーマーケット年次統計調査報告書」によれば、2021年7月~8月の国内にスーパーマーケットを保有する企業278社(回答企業)における食品ロスのうち、商品カテゴリ別では特に「総菜」が多く、次いで「水産」「畜産」の順に多くなっています。
小売業が食品ロス解消のためにできることは?
食品小売業における食品ロス廃棄量は、食品製造業(121万トン)、外食産業(81万トン)に比べれば少ないものですが、SDGsの観点からも経営の観点からも、さらなる減少に向けた取り組みが必要といえます。
総菜や生鮮食品を中心に、販売量を見越した精度の高い発注を行い、売れ残りを防いで、廃棄しなければならない食品ロスを削減し、利益向上につなげることが大切です。
食品ロス問題解決の為のデータ分析
食品ロス問題を解決するために、事業者が実践できる取り組みにとして、2つのアプローチが考えられます。
一つは、食品が過剰に生産、流通されないようにあらかじめコントロールすること、もう一つは、それでも過剰に出回ってしまった食品を、傷む前に必要な人に届けて消費してもらうことです。
ここでは、特に小売業者向けに食品ロス問題解決の為に有効なデータ分析について、ご紹介いたします。
精度の高い発注量計算と自動発注
まずは、第一段階として、食品を過剰に発注してしまわないよう、需要に見合った適正量で発注を行う必要があります。特に、日持ちのする加工食品だけでなく、野菜や精肉、鮮魚といった生鮮食品、総菜類を多く取り扱っている場合は、発注量が多すぎれば食品ロスに直結してしまいます。
たとえば、過去の販売データや天候などを元に、最適な発注量を計算して自動発注してくれるシステムを活用すれば、その季節の需要に見合った発注が効率よく行えるようになります。精度の高い発注量計算により、無駄な在庫の発生を抑え、廃棄しなければならない食品を減らすことが可能です。
食品廃棄管理
いくら計算精度の高い自動発注システムを導入していても、完璧に需要を予測することは困難です。しかし、だからといって対象の食品をただ廃棄しているだけでは、食品ロス問題を改善することはできません。
まずは、廃棄しなければならなくなった食品の種類や量、天候やイベントなどその他の条件を細かく把握することが大切です。正確に把握・管理できて初めて、発注量計算にフィードバックして改善につなげたり、廃棄しないための施策(フードバンクへの寄付など)を計画したりすることができるようになります。
日次・週次・月次などで、全体の廃棄量のほか、商品カテゴリ別にどこで廃棄が多いのかを可視化し、正確に把握できる体制を整える必要があるでしょう。
食品ロス問題に取り組むにはまずデータの可視化から
食品を取り扱う小売業者が食品ロス問題に取り組む際は、日持ちがせず廃棄につながりやすい総菜や生鮮食品を中心に、精度の高い発注計算と食品廃棄管理を実現することが大切です。たとえば、適正な発注量を元に自動発注してくれるシステムを活用して、過剰な在庫を抱えないことなどが挙げられます。
アイネスがご提供するデータ可視化・分析ソリューション「Visualized CDA」では、お客様の希望に合わせて、さまざまなデータをリアルタイムで可視化することができます。
・店舗別の売上高
・全体の売上の進捗率(年・月・週) ※KPIの達成度
・日別の売上高の予測・実績表示
・部門別の売上高・売上数
・売上高前年同月比と粗利率
・エリア別売上高(東北・関東など) など
まずは、自社の食品ロスの現状をデータで客観的に把握し、適正量を発注できる体制を整えていきましょう。
それでも、食品ロスが発生してしまいそうな時は、早目にフードバンクなどへ連絡して廃棄せずに済むような対応を取りましょう。その際も、データの可視化が役立つはずです。
データ可視化・分析ソリューション「Visualized CDA」の詳細は、こちらのページをご覧ください。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。ITでお悩みのご担当者様へ
弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。

関連記事