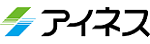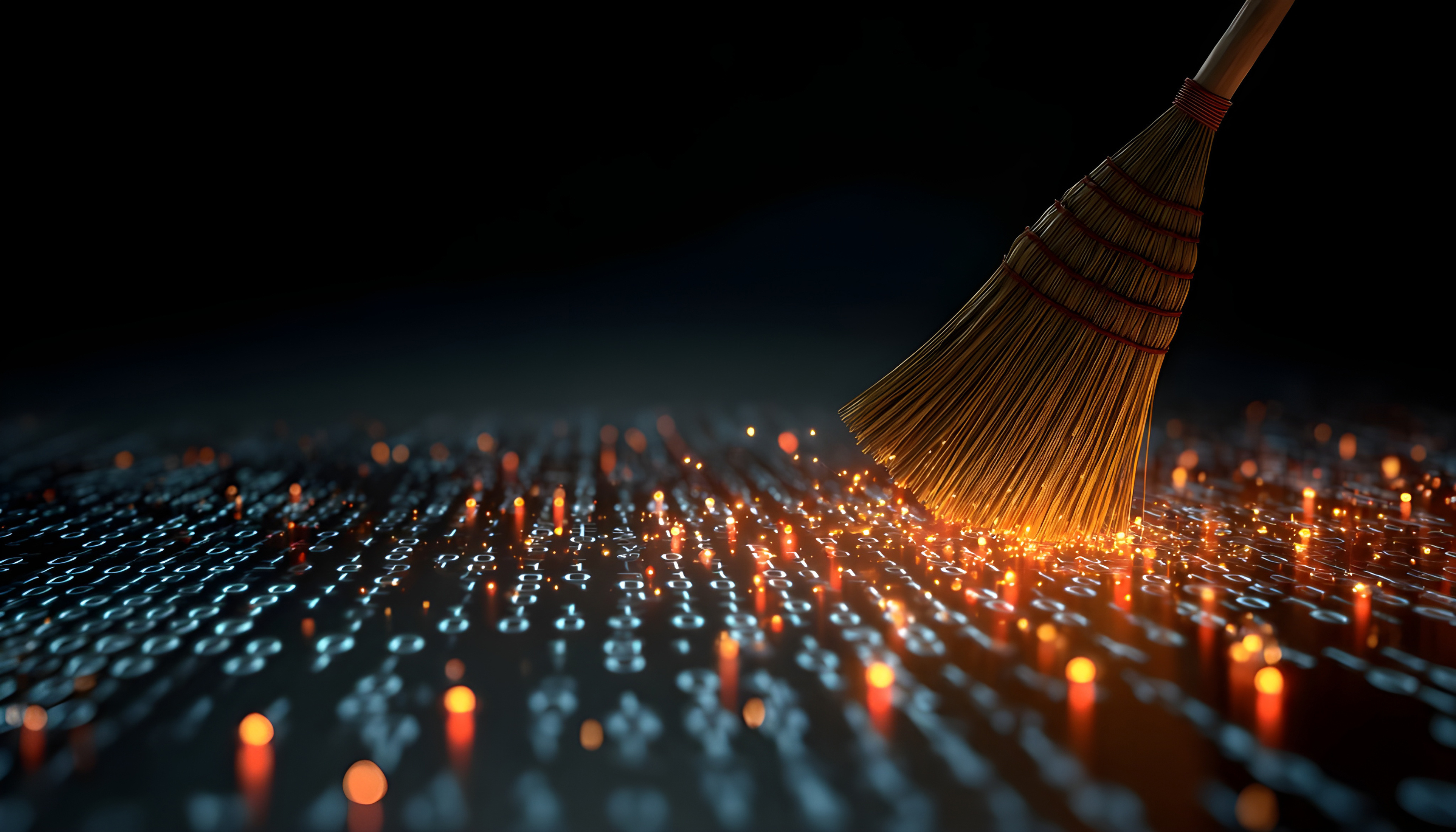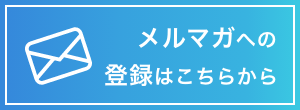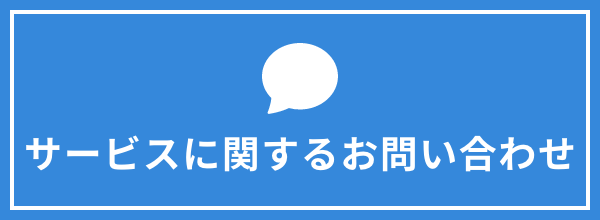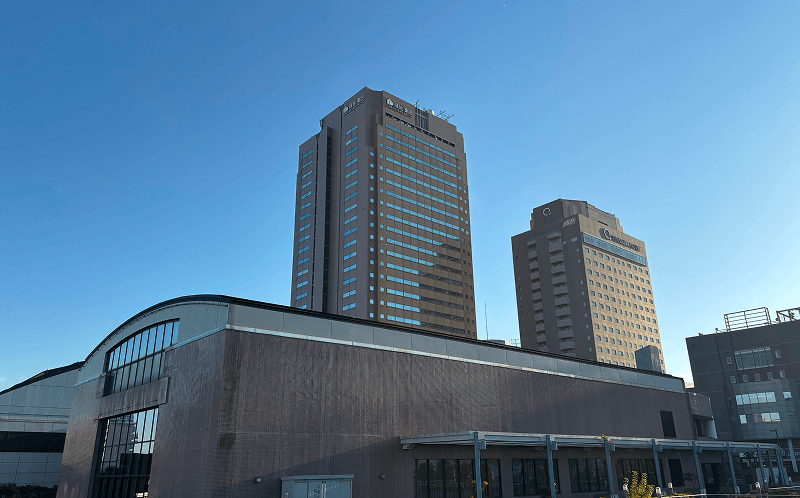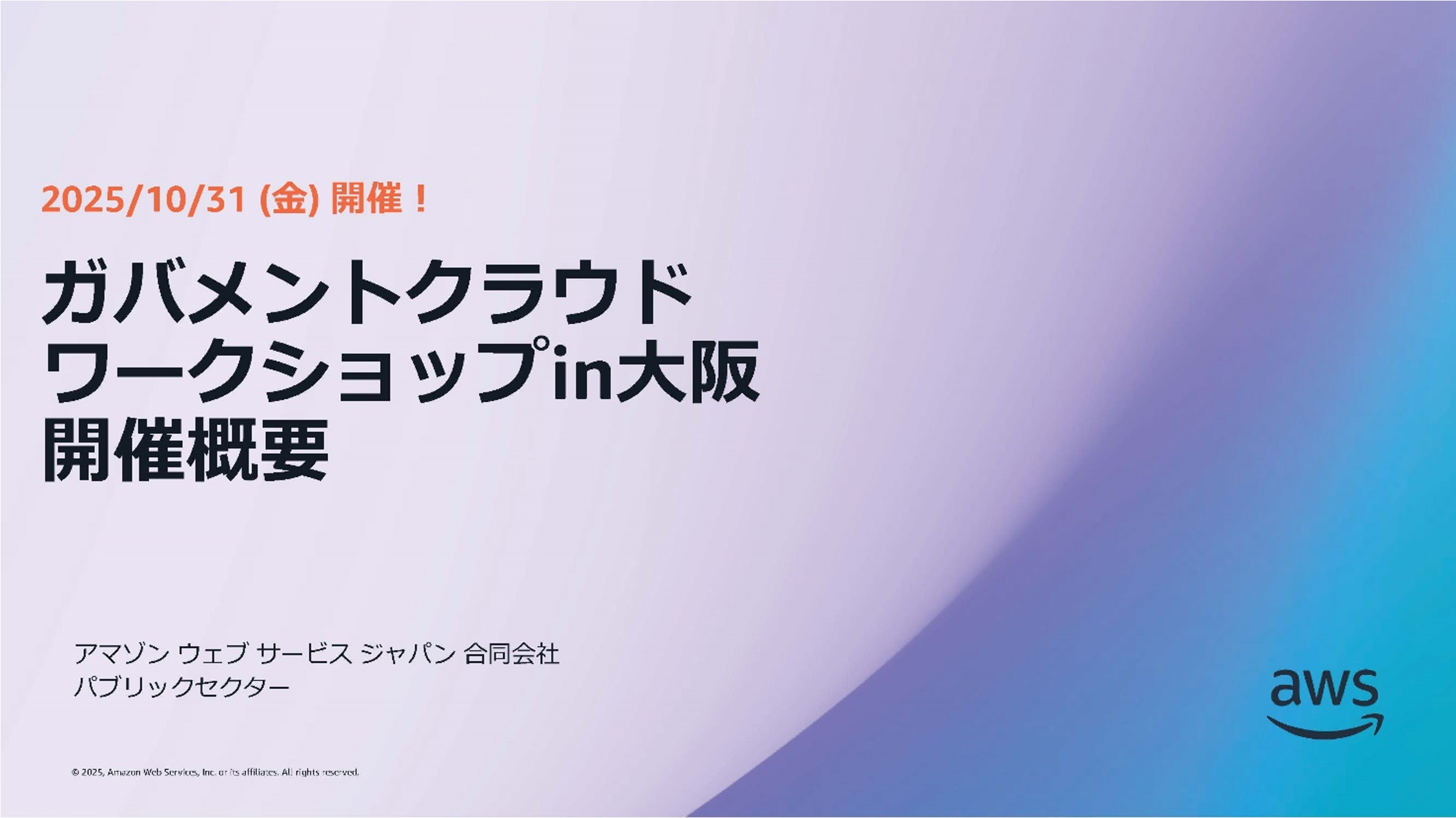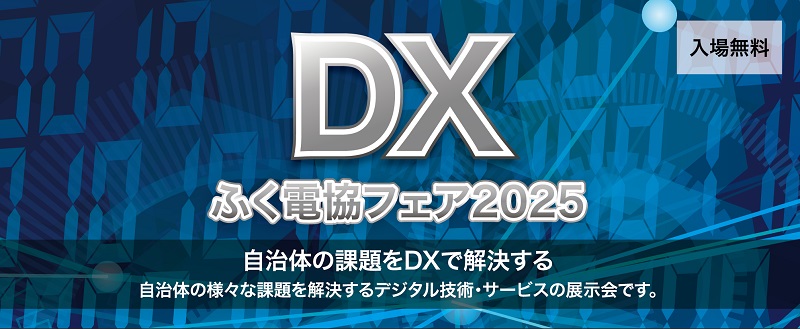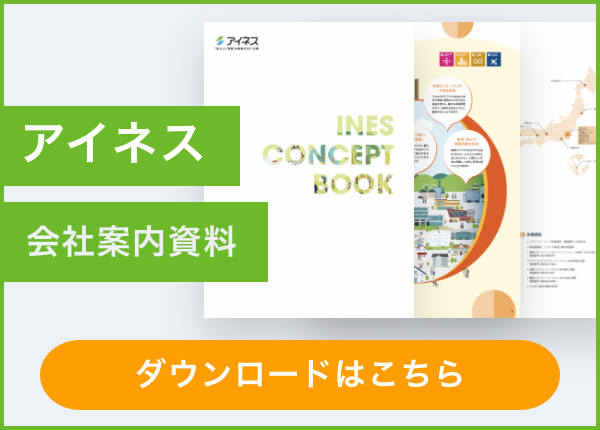- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- 文字起こしアプリ・ツールを使うメリットや注意点を解説
公開日
更新日
文字起こしアプリ・ツールを使うメリットや注意点を解説

文字起こしアプリ・ツールを使えば、手作業では多くの手間と時間がかかる音声のテキスト化作業の自動化が可能です。会議の議事録やインタビュー取材の記録など、音声データをテキスト化する幅広いシーンで役立ちます。
文字起こしアプリ・ツールには多くのメリットがある反面、使用上の注意点もあるため、「文字起こしアプリ・ツールを使うメリットと注意点を理解したい」「効率的に文字起こしアプリ・ツールを使うためのポイントを知りたい」という人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、文字起こしアプリ・ツールを導入するメリットやよく使われるシーン、使用上の注意点などを解説します。文字起こしアプリ・ツールを効果的に活用するコツにも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
文字起こしとは
そもそも文字起こしとは、録音された音声データをテキストデータに変換することです。対談やインタビューの記事を作成したり、会議や商談の議事録を作成したりする際に、録音したデータを文字に書き出す文字起こしが行われます。
文字起こしには、素起こし・ケバ取り・整文の3つの種類があります。
素起こし:録音した音声データをそのままテキストデータに変換する
ケバ取り:「えっと」「あのー」など不要な言葉をカットしてテキストデータ化する
整文:文章として意味が伝わりやすい形に整えてテキストデータ化する
手作業で文字起こしをする場合は、一般的に、ケバ取り・素起こし・整文の順に手間と時間がかかります。どの種類の文字起こしであっても、音声データを単に録音するよりも大変な作業です。
文字起こしアプリ・ツールとは
文字起こしアプリ・ツールとは、上記のような文字起こしの大変な作業を自動的に行ってくれるアプリ・ツールのことです。録音した音声データをアップロードしたり、マイクを使ってその場で音声を入力したりすると、AIが声を認識してテキストデータに変換します。
近年はAIの音声認識性能も向上しており、入力した音声データに対して精度の高いテキストデータを作成可能です。スマホ・タブレット・PCでダウンロードして使う文字起こしアプリが一般的ですが、ブラウザ上で使えるツールもあります。
文字起こしアプリ・ツールを使うメリット
文字起こし作業にアプリやツールを使うメリットには、以下のようなものがあります。
・ 会話に集中できる
・ リアルタイムで文字起こしできる
・ 文字起こしの負担・ミスを軽減できる
・ 議事録作成の負担を軽減できる
・ 迅速な情報共有が可能になる
・ 複数言語に対応できる
会話に集中できる
担当者が会話に集中できるのは、文字起こしアプリ・ツールを使うメリットのひとつです。インタビューや会議に出席してその場で文字起こしを行う場合、作業者は文字起こし作業に相当の集中力を使うため、会話の内容に集中する余裕はほとんどありません。
音声の文字起こしをアプリやツールに任せれば、その場で一生懸命文字に起こす作業をする必要はなくなります。会議や商談などのやり取りにも入りやすくなるでしょう。
リアルタイムで文字起こしできる
文字起こしアプリ・ツールを使えば、リアルタイムで文字起こしが可能です。手作業での文字起こしの場合、かなりのスキルがなければ会話のスピードについていくのは難しいでしょう。基本的には会話を録音して持ち帰り、あとで文字起こしをすることになります。
マイクで拾った会話をそのまま文字起こしできるアプリ・ツールなら、会話をしながら文字起こしができます。手作業での最終的なチェックと調整は必要ですが、すぐにテキストデータが必要なシーンにも使いやすいでしょう。
文字起こしの負担・ミスを軽減できる
文字起こしの負担とミスを軽減できるのも、文字起こしアプリ・ツールを使うメリットです。
まず、文字起こしアプリ・ツールを使えば、録音データを繰り返し聴きながらテキスト化する手間がかかりません。一般的に文字起こしには、音声データの長さの数倍の時間がかかるため、この時間が不要となるのは大きなメリットだといえます。
また、手作業で文字起こしをする際のミスを防止できるのもポイントです。文字起こしアプリ・ツールを使ってもミスは起こりますが、AIに学習させながら長期的に使っていけば、より精度の高い文字起こしができるようになります。
議事録作成の負担を軽減できる
文字起こし作業が必要になる代表的なシーンに、議事録作成があります。議事録作成時の文字起こしでは、単に音声をテキスト化するだけでは不十分です。誰が何を発言したのかを割り振り、議題ごとに内容を整理する必要があります。
文字起こしアプリ・ツールを使えば、声で話者を識別した書き分けや要約なども自動化可能です。クラウド上で編集できるものなら、関係者で共同作業もできます。
迅速な情報共有が可能になる
文字起こししたテキストデータを関係者に共有する際にも、文字起こしアプリ・ツールが役立ちます。
手作業で作成した文字起こしデータは、別途メール送付やクラウド保存など共有する作業が必要です。一方、文字起こしアプリ・ツールなら、同じアプリ・ツール内でデータを関係者に共有できます。手作業よりも手間と時間をかけずにデータを共有可能です。
複数言語に対応できる
外国語の音声データを手作業で文字起こしする場合、その言語が扱えるスタッフが対応する必要があります。外国語を扱えるスタッフが少ない企業・自治体においては、特定のスタッフに作業負荷が集中してしまうのは問題です。
文字起こしアプリ・ツールの中には多言語対応のものもあり、音声データを関係者が読みやすい言語に翻訳してテキスト化できます。外国語での会議やインタビューのデータを書き起こす機会が多い人には、必須の機能だといえるでしょう。
文字起こしアプリ・ツールがよく使われるシーン
文字起こしアプリ・ツールはさまざまなシーンで利用されます。文字起こしアプリ・ツールがよく使われるのは、以下の4つのシーンです。
・ 会議の議事録の作成
・ インタビューなど取材の記録
・ 講義・セミナーなどの記録
・ 面談・面接などの記録
会議の議事録の作成
会議や打ち合わせ、商談の議事録作成は、文字起こしアプリ・ツールがよく使われるシーンのひとつです。特に経営会議や役員会議では、発言内容をすべて議事録に記録するケースがあります。発言すべての書き起こしは手作業では難しいため、アプリやツールが便利です。
日頃の会議や商談では、文字起こしした結果を要約できるアプリ・ツールが役立ちます。長時間の商談や議題が多い会議でも、適切なアプリ・ツールを使えば重要なポイントをまとめたわかりやすい議事録が作成可能です。
定期ミーティングや月次報告など開催頻度が高い会議も、文字起こしアプリ・ツールを使って作成すれば、手間と時間をかけずに議事録を作成・共有できます。これまで議事録の作成に費やしていた多くの時間を、本業に使うことができるようになるでしょう。
インタビューなど取材の記録
インタビューなどの取材記録でも、文字起こしアプリ・ツールがよく使われます。
インタビューをしながら手作業で文字起こしをするのは現実的ではないため、録音データを持ち帰って文字起こしをするのが一般的です。文字起こしアプリ・ツールを使えば、インタビューと同時に文字起こしをしたテキストデータが仕上がります。
文字起こしアプリ・ツールは、対談の記録にも便利です。話者を判別できるものを使えば、あとで音声を聴きながら書き分ける手間が省けます。
講義・セミナーなどの記録
講義やセミナーなどのテキストデータ化にも文字起こしアプリ・ツールが便利です。
講義やセミナーなどの音声データは長時間になりやすく、手作業での文字起こしには大きな時間と労力がかかります。リアルタイムで文字起こしをしようとすると、内容に集中できないのもネックです。
文字起こしアプリ・ツールを使用すれば、長時間の音声データを効率的にテキスト化できます。見出し分けや要約ができるアプリ・ツールなら、文字起こしと同時に見返しやすいまとめ資料の作成も可能です。
面談・面接などの記録
面談や面接など、メモを取りにくいシーンの記録用にも文字起こしアプリ・ツールが役立ちます。
文字起こしアプリ・ツールを活用すれば、面談・面接時の音声を録音しておくだけで、会話の内容をテキスト化して整理可能です。会話中にメモを取る必要がなくなるので、より内容に集中しながら面談・面接が進められるでしょう。
特に採用面接など一定期間内に複数の候補者を評価する必要があるシーンでは、やり取りを素早くテキスト化できる文字起こしアプリ・ツールは便利です。テキストデータを比較することで、別の面接官が対応した候補者もフラットに評価できます。
文字起こしアプリ・ツールの注意点
文字起こしアプリ・ツールは便利な道具ですが、使用上の注意点もいくつか存在します。文字起こしアプリ・ツールを使用する際の主な注意点は、以下の4点です。
・ 読み取りは録音環境に左右されやすい
・ 専門用語は読み取りが難しい
・ 手直しが必要な場合がある
・ 媒体によって使えるアプリ・ツールが異なることがある
それぞれの注意点をチェックして、効率的に文字起こしアプリ・ツールを活用できるように準備しましょう。
読み取りは録音環境に左右されやすい
文字起こしアプリ・ツールによるテキスト化の精度は、録音環境に左右されやすい点には要注意です。テキスト化する音声データにノイズが多く入っていると、正確な読み取りができない可能性があります。
例えば、以下のようなシーンでの会話の録音データは、文字起こしアプリ・ツールを使ってもテキスト化の精度が低くなってしまうリスクがあります。
・ 参加者が多く発言が重なっているタイミングがある
・ 声が極端に小さい
・ 参加者の声のボリュームに極端な差がある
・ 環境音が大きく会話が聞き取りにくい
文字起こしアプリ・ツールの使用を前提に音声を録音する際は、テキスト化したい会話をできるだけクリアに記録できるように工夫しましょう。
専門用語は読み取りが難しい
音声が聞き取りやすいものであったとしても、一般的ではない用語・言い回しは意図した形でのテキスト化ができない可能性があります。専門用語が多い会議・商談などで使う際には注意が必要です。
具体的には、以下のようなものは意図したテキスト化が難しいと考えられます。
・ 固有の商品名・サービス名
・ 業界・企業特有の言い回し
・ 企業独自の略称
専門的な用語・言い回しを使う会議・商談で使う場合は、文字起こしアプリ・ツールの精度を上げるための工夫が必要です。
手直しが必要な場合がある
効率的に音声のテキスト化ができる文字起こしアプリ・ツールですが、その精度は完璧ではないため、手作業での見直しが必要です。出力されたテキストをそのまま活用するのではなく、最後には必ず人の目でチェックするようにしましょう。
特に人の目でのチェック時に意識すべきポイントは、以下のとおりです。
・「えっと」「あのー」といったケバが残っていないか
・ 記録不要な相槌やガヤまでテキスト化していないか
・ 誤変換している単語・言い回しはないか
・ 話者の誤認識はないか
・ テキスト化できずに抜け落ちているパートはないか
媒体によって使えるアプリ・ツールが異なることがある
文字起こしアプリ・ツールには、Windows・Mac・Android・iOSなど使用できるデバイスが限定されているものもあります。普段使っているデバイスでは機能しないアプリ・ツールを選ばないように気をつけましょう。
また、入力する音声データの形式にも指定があるものもあります。音声データにはMP3・MP4といった形式が存在するため、手持ちのレコーダーなどの仕様をチェックして入手しやすい音声データの形式を確認しておきましょう。
文字起こしアプリ・ツールを活用するコツ
文字起こしアプリ・ツールを効果的に使うためには、いくつかコツがあります。主なコツとして以下の4点を確認しておきましょう。
クリアな録音環境を用意する
前述のとおり、文字起こしアプリ・ツールのテキスト化の精度は、音声データの品質に大きく左右されます。ガヤや環境音などのノイズを極力抑え、テキスト化したい会話をできるだけクリアに録音できる環境づくりが大切です。
例えば、録音に使用するマイクは指向性が高いものが望ましいでしょう。発言を記録したい話者にのみ集中して音声を拾えるマイクを使用してください。オンラインでの会議などでは、ヘッドセットやイヤホンマイクの使用がおすすめです。
また、録音する場所も重要なポイントといえます。環境音が多い屋外や人混みなどは避け、できるだけノイズが少ないクローズな部屋で使うよう意識しましょう。
辞書機能やAIの学習機能を使って精度向上を図る
文字起こしアプリ・ツールの精度を上げるには、辞書機能やAI学習機能の活用が不可欠です。
特に専門的な用語・言い回しが多い会議・打ち合わせで使うのであれば、手軽に使える辞書機能を活用しましょう。辞書機能とは、あらかじめ用語・言い回しを登録しておくことで、指定したテキストに変換できるようにする機能です。
AI学習機能の性能は、アプリ・ツールによって差があります。使用頻度が多い場合は手作業による修正の手間もかかるため、文字起こしアプリ・ツールを選ぶときは、学習機能の性能が高いものを選びましょう。
手作業でのチェック・調整の工数を確保しておく
文字起こしアプリ・ツールで作成したテキストデータは、共有や活用をはじめる前に手作業でのチェック・調整が必要です。あらかじめ手作業によるチェック・調整の工数を想定して確保しておかなければ、不完全なテキストデータのまま使ってしまうリスクがあります。
無料版を利用して使用感を確認しておく
文字起こしアプリ・ツールの使用感は、実際に使ってみないとわからない部分もあります。また、アプリ・ツールの種類も多く、自社に最適なものを選ぶためには複数のアプリ・ツールを比較検討することが望ましいでしょう。
有料の文字起こしアプリ・ツールにも、一定の期間や一部の機能を無料で使えるものがあります。文字起こしアプリ・ツールで何ができるのかをイメージしたいときや、複数のアプリ・ツールを比較したいときは、無料版を使ってみてください。
まとめ
本記事では、文字起こしアプリ・ツールを使うメリットや注意点について解説しました。文字起こしアプリ・ツールを使えば、会議やインタビューなどの会話に集中しながら、音声の正確なテキスト化が可能です。
また、会議の議事録作成やインタビューなどの取材記録、講義・セミナー・面談などの記録時に役立ちます。単なる文字起こしではなく、話者の識別や要約ができるアプリ・ツールを使えば、活用しやすい資料を作成できるでしょう。
ただし、テキスト化の精度は、録音環境に大きく左右される点には要注意です。話者の発言だけを録音しやすい指向性マイクを採用し、ノイズが少ないクローズな環境で音声データを取るようにしてください。
なおアイネスでは、AIを活用した自治体相談業務支援サービス「AI相談パートナー」を通して、自治体における相談業務の効率化を支援しています。
AI相談パートナーのサービス機能
会話の自動テキスト化(文字起こし)機能
AI音声認識技術を用いて、会話内容をリアルタイムに自動でテキスト化(文字起こし)します。テキスト化した内容は保存できるので、相談記録票を作成する時に活用でき、そのまま関係者に共有可能です。
職員支援ガイダンス表示機能
相談対応中の会話内容に応じて、相談対応に役立つガイダンスを表示します。ガイダンス内容は、深堀してヒアリングすべき項目、関連行政サービス情報、関連法案等です。
記録票作成サポート機能
テキスト化された会話内容に対し、個人が特定される恐れのある情報を自動でマスキングします。
相談業務で必要とされる観点要約により、相談員の業務負荷を圧倒的に削減します。
AI相談パートナーは、低コストでのスモールスタートも可能です。文字起こしアプリ・ツールの導入を検討している自治体関係者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【お問い合せ先】
今回、ご紹介しましたアイネスの「AI相談パートナー」について、より詳しい内容をお知りになりたい方は、下記からお問い合わせください。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。 弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。
ITでお悩みのご担当者様へ

関連記事