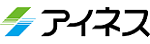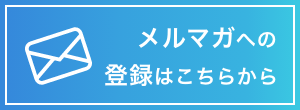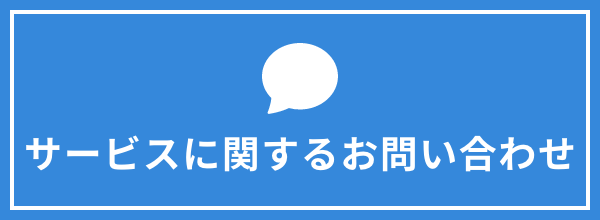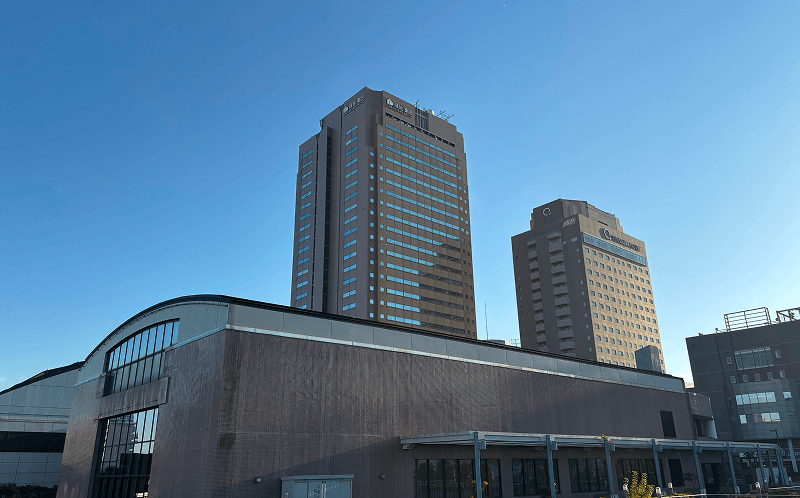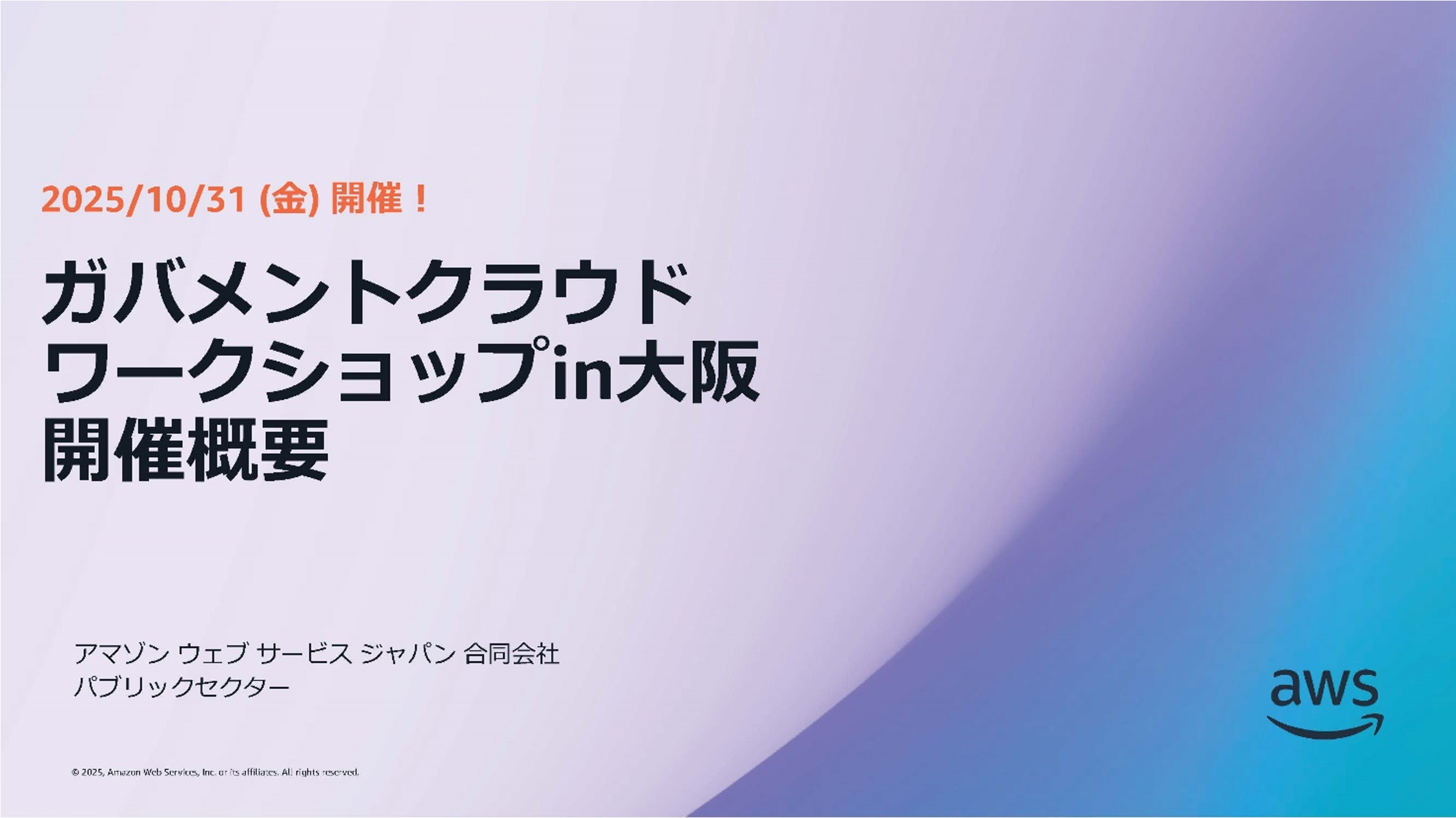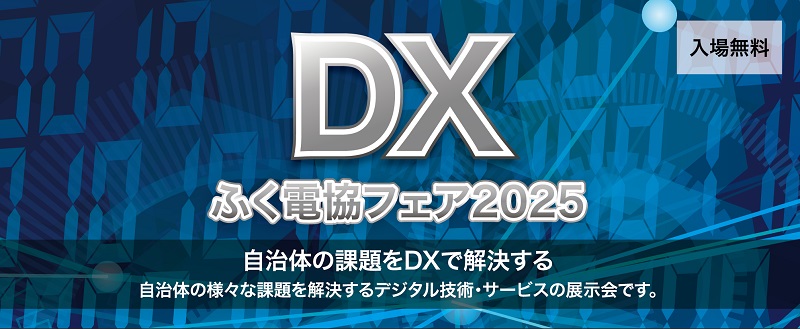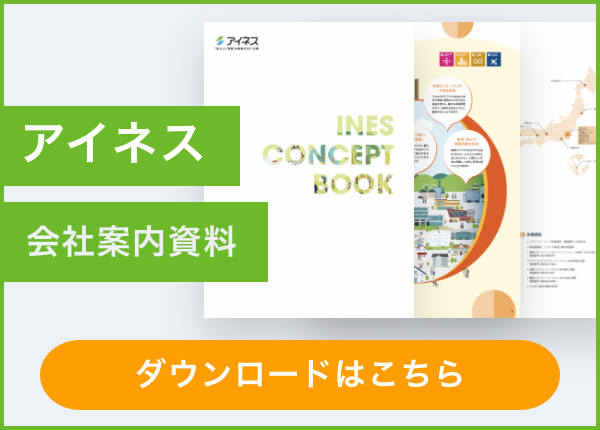- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- マスタ管理とは?重要性や導入方法、実践のポイントを解説
公開日
更新日
マスタ管理とは?重要性や導入方法、実践のポイントを解説

マスタ管理とは、企業が保有するマスタデータを一元管理する取り組みです。適切なマスタ管理を実施することで、マスタデータを効率的かつ正確に管理できるようになります。
一方、マスタ管理を実施するには手間と時間がかかるため、「マスタ管理の重要性やメリットを確認してから取り組みたい」「マスタ管理という「仕組み」を導入する手順を知りたい」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、マスタ管理とは何か、その重要性やメリットなどを解説します。マスタ管理という「仕組み」を導入する方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
マスタ管理(MDM)とは?
マスタ管理とは、企業の基幹業務に関わる「マスタデータ」を一元的に登録・整備・運用する仕組みや活動を指します。マスタデータとは、業務システムにおいて継続的に参照される固定的な情報のことで、たとえば「取引先マスタ」「品目マスタ」「社員マスタ」「顧客マスタ」などが代表例です。これらの情報は、販売・購買・生産・在庫・会計など複数の部門で日常的に利用され、システム全体の正確性や一貫性を保つ基盤となっています。
マスタ管理が適切に行われていないと、各部門で同じ取引先が異なる名称で登録されたり、在庫数の不整合が発生したりするなど、業務全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。とくに複数のシステムを併用している企業や、拠点・グループ会社をまたいだデータ連携が必要な組織においては、マスタデータの統一と精度管理が不可欠です。
ERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理システム)、SFA、会計ソフトなど、さまざまな業務アプリケーションが同じマスタデータを参照する環境では、データの不整合が即業務停止や誤った意思決定に繋がるリスクがあります。そのため、マスタ管理の戦略的な取り組みが必要です。
マスタ管理の重要性
マスタデータは、単なる住所録や名簿のようなものではなく、繰り返し利用される基幹データです。データの登録・更新・削除といった操作一つひとつが各部門の業務に波及し、最終的には経営判断や財務報告、顧客対応の質にまで影響を及ぼすため、マスタ管理の質が企業の競争力に直結するといえます。
たとえば、受注伝票で取引先名を入力する際に、マスタに誤った情報が登録されていれば、配送ミスや請求ミスの原因になります。また、品目マスタの単位換算が間違っていれば、生産計画や在庫管理に狂いが生じ、余剰在庫や欠品といったロスが発生する可能性もあるでしょう。こうしたミスを防ぎ、正確で一貫した業務プロセスを実現するためには、信頼性の高いマスタ管理体制が欠かせません。
マスタ管理のメリット
マスタ管理の主なメリットは、以下の3点です。
・業務の効率や正確性が向上する
・データガバナンスを強化できる
・データ分析の精度が向上する
各メリットについて、詳しくチェックしてみましょう。
業務の効率や正確性が向上する
マスタ管理によって、同じ情報が各部門やシステム間で統一されると、業務の無駄な確認作業や二重入力の削減につながります。
たとえば、営業部門が入力した取引先情報を、経理部門や物流部門も同じフォーマットでそのまま活用できれば、入力ミスや情報の食い違いが大幅に減ります。これにより、業務の手戻りが減少し、担当者の負荷も軽減可能です。
また、品目や顧客情報などのデータが正確に管理されていることで、在庫管理や請求処理、受注処理といった日常業務がスムーズに行えるようになります。マスタの不備による伝票エラーや請求漏れといったトラブルも回避でき、トータルで見れば組織全体のパフォーマンスの底上げが期待できるでしょう。
とくに複数拠点で業務を展開している企業にとっては、共通のマスタが存在することが業務の標準化にもつながり、新入社員や異動者の教育コスト削減にも貢献します。
データガバナンスを強化できる
マスタ管理は、企業のデータガバナンス体制を強化する上でも重要です。データガバナンスとは、企業内に蓄積されるデータを正しく管理・統制し、必要なときに正確に利用できるようにするための仕組みやルールのことを指します。マスタデータが統一されていなければ、部門ごとに異なるルールや命名規則で情報が乱立し、組織全体として一貫した判断や対応が難しくなります。
マスタ管理を行うことで、データの登録・更新・削除に関するルールが明文化され、誰が、いつ、どのような情報を取り扱っているかを可視化できます。これにより、不正操作の防止や業務の透明性が向上し、内部統制や監査対応にも強い仕組みを構築することができます。
また、ガバナンスの強化は、企業の対外的な信頼性にもつながります。取引先や監査法人、株主などに対しても、「情報を正確に管理している企業」として評価されやすくなり、コンプライアンス対応にも有利に働くでしょう。
データ分析の精度が向上する
近年では、BIツールやデータ分析基盤を活用して、経営戦略や業務改善に活かす企業が増えています。しかし、分析の前提となるデータが不完全であれば、どれだけ高度な分析を行っても正しい結論は導き出せません。マスタ管理を徹底することで、各データの整合性や粒度が揃い、分析に適したデータセットが形成されやすくなります。
たとえば、同じ顧客が「㈱○○」「株式会社○○」「○○(株)」といった形で複数登録されていると、集計時に別顧客として扱われてしまい、正しい傾向分析や売上比較ができません。マスタ管理によって名称やコード体系が統一されていれば、顧客単位・商品単位の集計が正確に行えるようになります。
マスタ管理という「仕組み」を導入する方法
マスタ管理という「仕組み」を導入する方法を以下の4つのステップで解説します。
1.目的の明確化と課題の洗い出しを行う
2.取り扱うデータの現状分析を行う
3.データを収集・統合する
4.運用・管理体制を整える
各ステップでの実施事項を確認しておきましょう。
目的の明確化と課題の洗い出しを行う
マスタ管理を導入するうえで最初に行うべきは、「何のためにマスタを整備するのか」という目的の明確化です。単なる業務改善の一環として捉えるのではなく、「何を解決したいのか」「どの業務に効果が出るのか」といった視点で目的の明確化と課題の洗い出しを行う必要があります。
たとえば、「請求ミスを減らしたい」「在庫の二重登録を防ぎたい」「拠点ごとに異なる顧客情報を統一したい」など、具体的な課題を整理しましょう。それらの課題を解決するために、どのマスタデータを対象とするか、どの範囲で管理するかを明文化しておくと、後工程のシステム設計やルール策定がスムーズに進みます。
目的の明確化と課題の洗い出しの段階では、業務担当者だけでなく、IT部門や経営層、監査部門などの関係者とも意識合わせをしておくことが大切です。
取り扱うデータの現状分析を行う
要件が固まったら、次に自社で扱っているマスタデータの現状の把握が必要です。ここでは、「どこに、どんなデータが、どのような形式で存在しているか」を洗い出す棚卸し作業が求められます。
多くの企業では、同じ情報が複数のシステムやExcel、紙帳票などに重複して存在しており、命名ルールや管理項目が統一されていないケースも珍しくありません。そのような状況を把握せずに新しい管理方法を導入すると、さらに混乱を招く可能性があります。
この段階で重要なのは、現状の課題点を明確にすることです。たとえば、「部署ごとに同一の取引先が別名義で登録されている」「品目コードに命名ルールがないため検索しづらい」「更新履歴が残っていない」などの問題を洗い出し、対処すべき優先順位をつけておくとよいでしょう。
データを収集・統合する
現状分析をもとに、次に行うのが「データの収集と統合」です。複数の場所に分散しているマスタ情報を整理し、信頼できるマスタデータを作成します。
統合作業は手間がかかりますが、この工程を怠るとせっかくマスタ管理の仕組みを導入しても精度の低いデータをもとに業務が進んでしまい本末転倒です。専門のマスタ統合ツールや、ETL(抽出・変換・ロード)機能を持つシステムを活用することで、精度と効率を両立した統合が実現できます。
運用・管理体制を整える
マスタ管理は、導入して終わりではありません。継続的に品質を保つための運用・管理体制の整備が求められます。
まず、マスタデータの登録・更新・削除に関する明確なフローと承認ルールを設ける必要があります。誰が登録し、誰が承認し、どのタイミングで反映されるのかを文書化しておくことで、属人的な運用を排除し、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
次に、マスタ管理の担当部門や責任者を明確にし、定期的に品質チェックや棚卸しを実施する体制を作ることが重要です。また、運用ルールが現場に浸透していないと形式だけの管理になってしまうため、マニュアルや教育コンテンツの整備も並行して行いましょう。
マスタ管理(MDM)導入のポイント
最後にマスタ管理(MDM)を導入する際のポイントとして、以下の3点を解説します。
・目標を設定し関係者全体で取り組む
・マスタ管理専用ツールを活用する
・ルールを定めて運用する
それぞれのポイントを整理して、自社での取り組みに活かしてください。
目標を設定し関係者全体で取り組む
マスタ管理を単なるITプロジェクトや業務改善の一環と捉えるのではなく、全社で共通の目標を設定し、関係者全体で取り組む姿勢が必要です。
マスタデータは複数の部門にまたがるため、情報システム部門だけでなく、営業・購買・会計・生産管理など、各部門の協力が不可欠です。部門ごとに異なる立場や課題を尊重しながら、共通のルールを設けていきましょう。プロジェクト初期の段階から現場担当者を巻き込み、業務への影響やメリットを共有することで、制度の定着と運用の実効性が高まります。
マスタ管理専用ツールを活用する
マスタ管理を手作業やExcelベースで行っている企業では、属人化や処理ミス、管理コストの増加といったリスクが高くなります。マスタ管理専用ツールを活用し、マスタ管理の効率化と精度向上を図ることが効果的です。
たとえば、ワークフロー機能を備えたマスタ登録システムを導入すれば、申請→承認→登録→反映といった一連の流れを自動化できます。入力チェックや重複判定、履歴管理などの機能を備えたマスタ管理専用ツールを使うことで、データの整合性や透明性を高いレベルで保つことが可能です。
ルールを定めて運用する
どれだけ高度な仕組みやツールを導入しても、それを支える運用ルールが必要です。
また、マスタ管理に関する社内ルールは、IT部門が一方的に定めるのではなく、現場業務を熟知した担当者と協議しながら策定するのが理想です。さらに、ルールを守るための仕組みとして、教育・研修、マニュアル、FAQ整備、定期的な棚卸しや監査も欠かせません。
まとめ
本記事では、マスタ管理とは何か、重要性やメリット、マスタ管理という「仕組み」を導入する手順などを解説しました。マスタ管理は、業務の効率・正確性を向上させるために必要です。自社のデータ管理上の課題を明確にし、それを解決できるマスタ管理を計画・実践しましょう。
「マスタデータの不整合や重複が生じている」「分散されたデータ統合のために時間とコストがかかる」といった課題を抱えている企業には、アイネスの「Aerps MASTER Enterprise」がおすすめです。マスタデータ管理(MDM)により、企業が保有するデータを一元管理し、品質と正確性を保ちます。
Aerps MASTER Enterpriseについてのお問い合わせはこちら
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。 弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。
ITでお悩みのご担当者様へ

関連記事