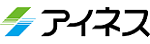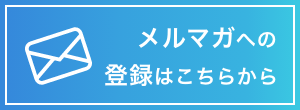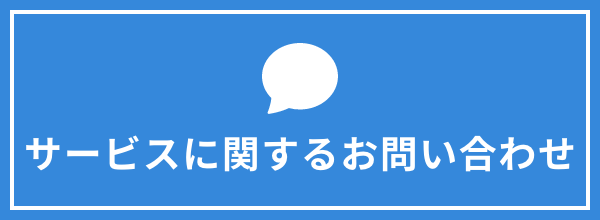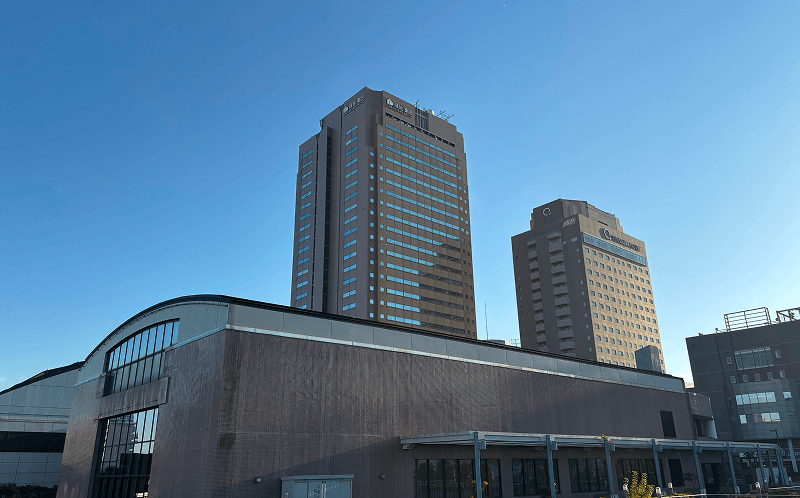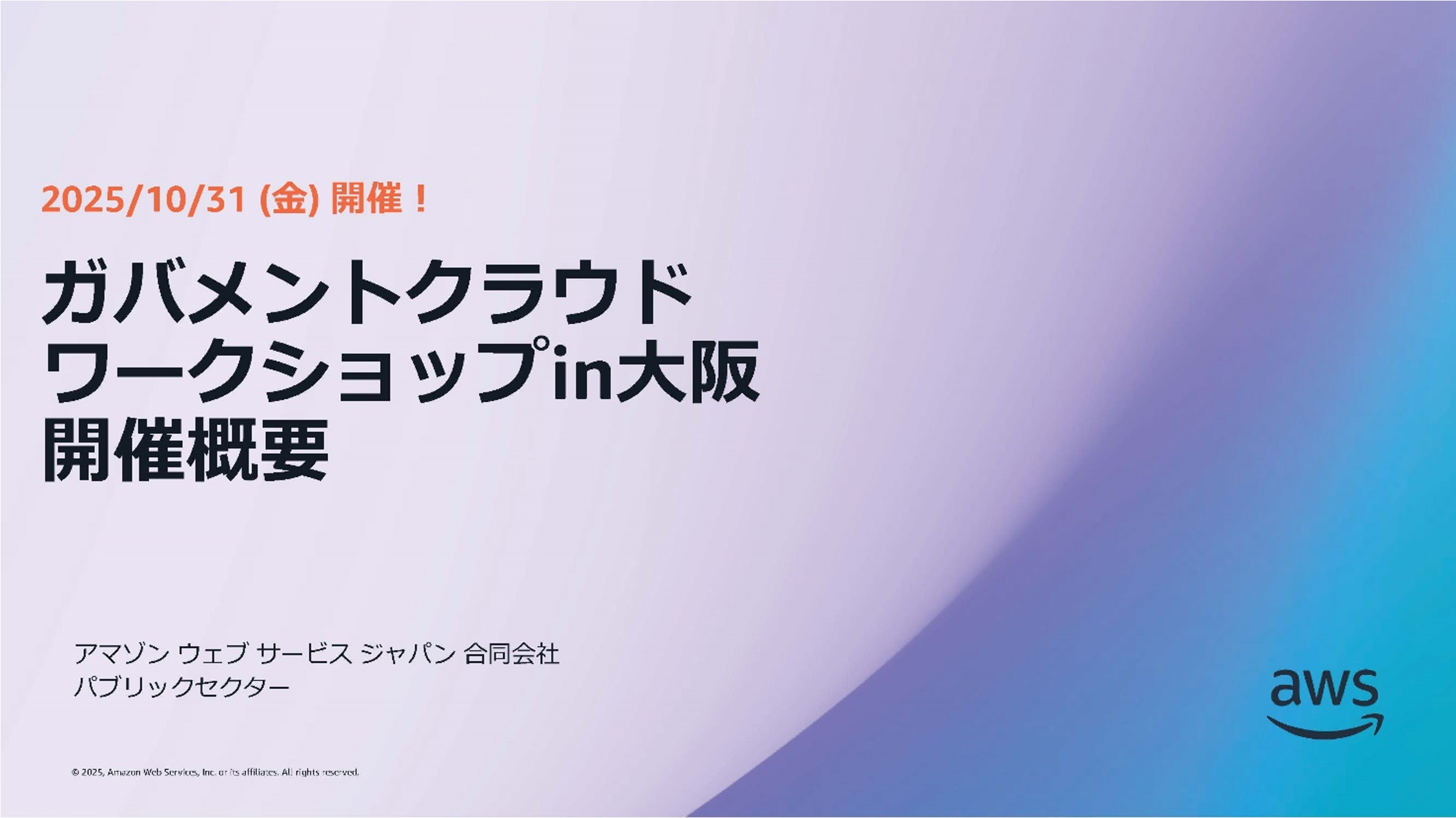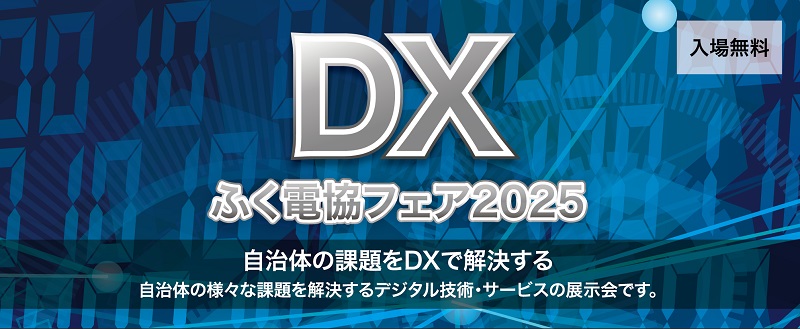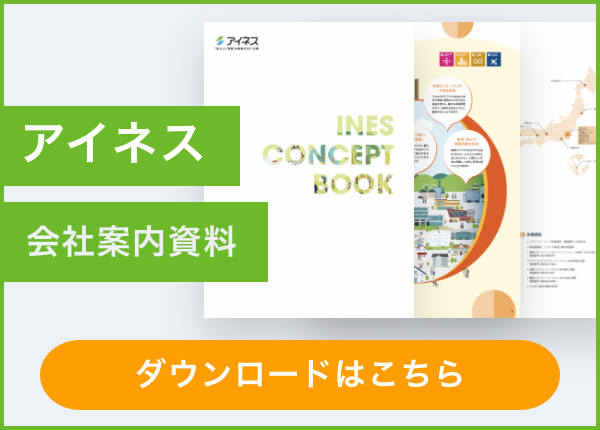- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- SAPとは?システムの特徴やメリット・デメリットを解説
公開日
更新日
SAPとは?システムの特徴やメリット・デメリットを解説

SAPとは、世界的なシェアを誇るSAP社のERP製品の1つです。特徴的なモジュール型構造により、業務の効率化や内部統制の強化、効果的なデータ活用などを実現できます。
一方、SAPの導入には高額なコストがかかり、運用には一定のスキル・ノウハウが求められるため、「まずはSAPの概要を知りたい」「SAP導入のメリット・デメリットを確認してから検討したい」といった方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、SAPとは何か、特徴や導入のメリット・デメリットなどを解説します。導入方法も紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。
SAPとは?
SAP(エスエーピー)は、ドイツに本社を置くSAP社が提供するERP製品の1つで、企業の会計・人事・物流・販売・製造など、あらゆる業務の統合・最適化が可能です。日本国内でも製造業や小売業を中心に広く導入が進んでいます。
企業の経営において情報の一元管理や業務プロセスの標準化は、持続的な成長や効率化を実現する上で欠かせない課題です。とくに複数の部署・拠点・国をまたぐような企業活動では、情報が分断されていると非効率やミスにつながります。
こうした背景のもと、注目されているのがERP(統合基幹業務システム)であり、その中でも圧倒的な世界シェアを誇るのがSAPです。
ERPとは?
ERPとは「Enterprise Resource Planning:統合基幹業務システム」の略語です。企業が持つあらゆる経営資源などを、部門ごとの個別管理ではなく、一元的に統合・管理しようという考え方から生まれました。従来のような部門ごとのサイロ化された業務を排除し、業務全体のスピードと精度を高めるのがERPの大きな目的です。
グローバル展開や多拠点管理を行う企業では、国や地域ごとの言語・通貨・会計基準の違いにも対応する必要があります。ERPはこれらを標準機能として備えることで、企業全体の意思決定を支える重要な仕組みとなっています。
SAPの特徴
SAPは、ERP分野において世界トップクラスの実績を誇るソフトウェアブランドです。製造業・小売業・金融業・医療業界など、多様な業種に対応する柔軟性を持ち、100以上の国や地域で数万社以上の導入実績があります。
最大の特徴は「モジュール型アーキテクチャ」です。SAPは会計・人事・販売・購買・生産管理などの業務領域ごとにモジュールを分け、それぞれが独立しつつも密接に連携する仕組みになっています。
また、SAPは多言語・多通貨への対応力にも優れており、各国の税制や会計基準への対応も充実しています。グローバル展開する企業にとって、現地と本社間の情報共有や統一運用が容易になる点も大きな利点です。
さらに、SAPはセキュリティや内部統制の観点でも高い信頼性を持ち、金融・医療などの高いガバナンスが求められる業界でも積極的に採用されています。ERPの導入を通じて、企業の信頼性やコンプライアンス対応力を強化するという面でも大きな価値を提供しているといえるでしょう。
SAPを構成するモジュール
ここでは、SAPの主要な3つのモジュールとその他のモジュールについて順に解説していきます。
・ロジスティクスモジュール
・財務会計モジュール
・人事モジュール
各モジュールの役割や機能を確認しておきましょう。
ロジスティクスモジュール
ロジスティクスモジュールは、SAPの中でもとくに製造業や流通業で重宝される領域です。購買管理・在庫管理・販売や出荷・生産計画・倉庫管理などを担うモジュールで構成されています。
主に以下のようなものが挙げられます。
・MM(Materials Management:資材管理)
・SD(Sales and Distribution:販売管理)
・PP(Production Planning:生産計画管理)
・EWM(Extended Warehouse Management:倉庫管理)
MMモジュールでは、発注から納品・検収・請求までの一連の購買業務を一元管理できます。SDモジュールでは受注から出荷・請求書発行・入金管理までをカバーし、販売活動の効率化が可能です。
EWMは倉庫内の作業指示やピッキング、ロケーション管理などの高度な業務にも対応し、物流の現場効率を大幅に改善します。ロジスティクスモジュールにより、在庫最適化、納期短縮、コスト削減といった課題解決が可能です。
財務会計モジュール
財務会計モジュールは、企業の資金の流れを一元的に把握・管理するための中核的なモジュール群です。主に以下のようなものがあります。
・FI(Financial Accounting:財務会計)
・CO(Controlling:管理会計)
・FSCM(Financial Supply Chain Management:財務サプライチェーン管理)
FIモジュールは、仕訳・元帳管理・決算処理・売掛金/買掛金管理・固定資産管理など、会計業務全般をカバーするのが役割です。COモジュールでは、原価計算や部門別損益の把握、プロジェクト別収支管理といった分析業務に対応し、経営判断に役立つ情報を提供します。
FSCMを活用すれば、資金繰り予測や信用管理、回収プロセスの最適化といった高度な財務戦略にも対応可能です。財務会計モジュールによって、リアルタイムな財務情報の把握と、会計監査・内部統制の強化が同時に実現できます。
人事モジュール
人事モジュール(SAP HCM)は、従業員のライフサイクル全体をカバーし、統合的な人材管理ができます。採用から配置・昇進/評価・給与計算・勤怠管理・離職後の手続きに至るまで、あらゆる人事関連業務を効率化します。
代表例は以下のとおりです。
・PA(Personnel Administration:人事管理)
・OM(Organizational Management:組織管理)
・PY(Payroll:給与計算)
・TM(Time Management:勤怠管理)
PAでは従業員の基本情報や契約情報を管理し、OMでは組織構造や上司・部下の関係性を定義します。PYは税金・保険料を含めた給与計算を自動化し、TMは打刻データや休暇管理をシステム化するのが役割です。
タレントマネジメント機能を活用すれば、スキルマップの作成や教育訓練計画、後継者候補の可視化など、戦略的人事施策にもつなげることができます。
その他のモジュール
SAPには、会計・人事・物流以外にも、さまざまな業務に対応した多彩なモジュールが存在します。代表的なものを以下に紹介します。
・QM(Quality Management):製品やサービスの品質管理、検査計画、不良品処理などを一元管理
・PM(Plant Maintenance):設備の保守点検・保全業務を支援し、機器の稼働率向上を実現
・PS(Project System):プロジェクトの計画立案から原価管理・進捗管理までをトータルサポート
・CRM(Customer Relationship Management):顧客情報を管理し、営業活動や問い合わせ対応を最適化
・BI(Business Intelligence):蓄積されたデータを分析し、経営層向けのレポートやダッシュボードを生成
これらのモジュールは個別にも導入可能ですが、全体として連携することで、企業活動をデジタルで一貫性のある流れとして構築することができます。
SAPを導入するメリット
SAPを導入する主なメリットとして、以下の5点について解説します。
・業務プロセスの効率化が図れる
・効率的なデータ処理が実現できる
・作業履歴の管理により内部統制を強化できる
・社会的信頼性の向上が期待できる
・ビッグデータの活用ができる
それぞれのメリットの詳細をチェックしておきましょう。
業務プロセスの効率化が図れる
SAPを導入すれば、自社の業務フローを効率化できます。これまで属人的に処理されていた業務がシステム化され、担当者が変わっても業務の品質が維持されやすくなります。
たとえば、受注から出荷・請求・入金に至るまでの販売プロセスが一気通貫で自動化されることで、手作業によるミスや確認作業の負担が大幅に軽減されます。購買や在庫管理、生産管理なども同様に、重複処理や転記作業を排除でき、業務スピードと正確性が格段に向上するでしょう。
効率的なデータ処理が実現できる
SAPでは、すべてのデータが統一された基幹システム上で管理され、データの一元化を実現することができます。たとえば、販売部門が入力した受注データがそのまま在庫管理や会計処理に反映され、手動入力や二重登録の必要がなくなります。
データの二重管理や整合性チェックにかかる時間を削減できる点は、企業にとって大きな効率化効果をもたらします。加えて、リアルタイムで情報を取得・分析できるため、経営判断のスピードが向上し、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できる体制を構築することができます。
作業履歴の管理により内部統制を強化できる
SAPでは、各ユーザーの操作履歴や業務の変更記録が詳細に自動保存されるため、内部統制や監査対応に有効です。とくに金融業や上場企業など、コンプライアンスが厳しく求められる業界では、トレーサビリティの高さが重視されます。
さらに、ワークフロー機能を活用することで、承認プロセスやアクセス権限の管理も一元的に行え、不正防止や権限と責任の明確化にも寄与します。操作ミスや不正アクセスが発生した場合でも、即座にログを遡って原因を特定することができ、迅速な対応が可能です。
社会的信頼性の向上が期待できる
SAPは、世界中の有力企業やグローバル企業が採用している信頼性の高いシステムです。企業がSAPを導入しているという事実自体が、「経営体制の透明性」や「国際的な業務運用基準への準拠」を示す指標となり、対外的な信用を高める要素となるでしょう。
とくに海外との取引が多い企業や、多国籍企業のグループ会社などでは、SAPのようなグローバル標準システムの導入が強く求められます。
ビッグデータの活用ができる
SAPの最新バージョン「SAP S/4HANA」は、高速なインメモリデータベース技術により、膨大なデータをリアルタイムで処理・分析することが可能です。これにより、企業内外に蓄積されたデータを活用した高度な意思決定が実現できます。
たとえば、販売データや購買履歴、生産実績、顧客動向などを統合的に分析し、需給予測やプロモーション施策の最適化、設備保守の予兆管理など、多様な業務に応用可能です。また、BI(Business Intelligence)ツールやAI分析ツールとの連携により、経営戦略の立案やKPIモニタリングを迅速かつ正確に行えます。
SAPを導入するデメリット
SAP導入のデメリットや注意点として、以下の3点を紹介します。
・導入と運用にコストがかかる
・運用スキルの習得に時間がかかる
・SAPの機能を理解する必要がある
各デメリットをチェックして、導入検討に役立ててください。
導入と運用にコストがかかる
SAPは高度なシステムであるため、導入費用・運用費用ともに高額になりやすい傾向があります。まずライセンス費用に加えて、要件定義・開発・テスト・教育・本番移行といった一連のプロジェクト工程に多大な工数とコストが発生する点には注意が必要です。
また、SAPは自社の業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能な一方で、標準機能での運用に収まらない場合は追加開発やアドオンの導入が必要となります。これは、コストが膨らむ要因の1つです。クラウド版であっても、年間のサブスクリプション料金や保守サポート費用が継続的に発生します。
運用スキルの習得に時間がかかる
SAPは非常に多機能かつ業務横断的な構造をしており、その分操作や設定内容も複雑です。導入後すぐにすべての社員が使いこなせるわけではなく、一定の習熟期間と教育投資が必要となるでしょう。
また、社内にSAP経験者がいない場合は、外部パートナーに依存する場面も増え、ナレッジが蓄積されにくいという課題もあります。導入後も継続的な教育プログラムや、サポート体制の整備が必要です。
SAPの機能を理解する必要がある
SAPは多くの業務をカバーできる反面、その機能や構成を正しく理解しなければ、期待通りの効果を得られません。さらに、独自の開発言語である「ABAP」や、トランザクションコードによる画面遷移など、他のシステムとは異なる操作体系に慣れる必要があります。
そのため、導入前の段階で十分な教育機会を設け、IT部門と業務部門が連携して設計・運用できる体制を構築することが不可欠です。
SAPの導入方法
SAPの導入方法を以下の6つのステップに分けて解説します。
1.導入目的を明確にする
2.導入する製品を選ぶ
3.自社に必要な機能を選定する
4.SAPをインストールする
5.パラメータを設定する
6.ABAPで必要な機能を開発する
それぞれのステップで実施すべき内容を確認しておきましょう。
導入目的を明確にする
最初に行うべきは、「何のためにSAPを導入するのか」を明確にすることです。たとえば業務効率化を狙うのか、経営管理レベルを上げたいのか、グローバル統一基盤を構築したいのかによって、必要な機能やスケジュールは大きく変わります。目的を関係者で共有し、ブレない導入方針を立てておきましょう。
導入する製品を選ぶ
SAPには複数の製品体系があり、自社に合ったものの選定が重要です。大企業向けには「SAP S/4HANA」、中堅・中小企業には「SAP Business One」や「SAP Business ByDesign」が用意されています。オンプレミス型とクラウド型の選択もあり、予算やスケーラビリティ、社内のITリソースに応じて慎重に選定しましょう。
自社に必要な機能を選定する
会計や人事、在庫、購買など、SAPには多様なモジュールがありますが、すべてを同時に導入する必要はありません。自社にとって本当に必要な業務領域を洗い出し、段階的に導入するのが現実的です。たとえば、まずは財務会計から導入し、その後販売や購買モジュールへと拡張するなど、フェーズを分けることでリスクと負荷を抑えることができます。
SAPをインストールする
SAPの製品形態によって導入作業は異なります。クラウド型の場合、ベンダー側で環境が提供されるため導入は比較的スムーズですが、オンプレミスの場合はサーバー構築やネットワーク設計、セキュリティ対策など、事前準備が多くなります。導入前には、インフラ面の要件定義も並行して進めておきましょう。
パラメータを設定する
SAPでは、各企業の業務ルールに合わせて多数のパラメータを設定可能です。請求タイミング・伝票処理のフロー・承認ルートなど、細かな設定が全体の業務効率に直結します。カスタマイズに頼らず、可能な限り標準機能とパラメータ設定だけで対応することが、保守性の高い運用を実現するためのポイントです。
ABAPで必要な機能を開発する
標準機能では対応できない特殊業務については、SAPの専用言語「ABAP」を用いて独自開発(アドオン)を行います。ただし、過度なアドオンはバージョンアップ時の障害リスクや保守負荷を高めるため、本当に必要な機能に絞り込むことが重要です。
SAP「2027年問題」とは?
SAPの従来型ERP「SAP ERP 6.0」は、2027年末でメーカーのサポートが終了予定となっており、SAPの「2027年問題」と呼ばれています。多くの企業は、最新の「SAP S/4HANA」への移行を求められていますが、移行には多額の費用や時間がかかるため、対応が進んでいない企業も多いのが現状です。これからSAPを導入する企業は、S/4HANAを前提とするため、2027年問題の影響はほとんど受けません。
まとめ
本記事では、SAPの機能や導入メリット・デメリット、導入方法などについて解説しました。SAPの導入により、業務の効率化や内部統制の強化などが期待できます。一方、導入にはコストがかかり、運用には一定のスキルやノウハウが必要となる点には注意が必要です。
SAPのようなERPソリューションの導入でお困りの場合にはアイネスの「ERP導入支援サービス」がおすすめです。経験豊富なコンサルタントが、お客様の抱える課題を解決するためのERPソリューションを提案、導入のサポートを行います。
「グローバルなシステムを構築したい」「短期間で基幹業務システムを導入したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。
ERP導入支援サービスに関するお問い合わせはこちら
【関連記事】
SAPとその他のERPの違いは?選び方や導入時の注意点などを解説
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。 弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。
ITでお悩みのご担当者様へ

関連記事