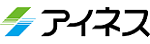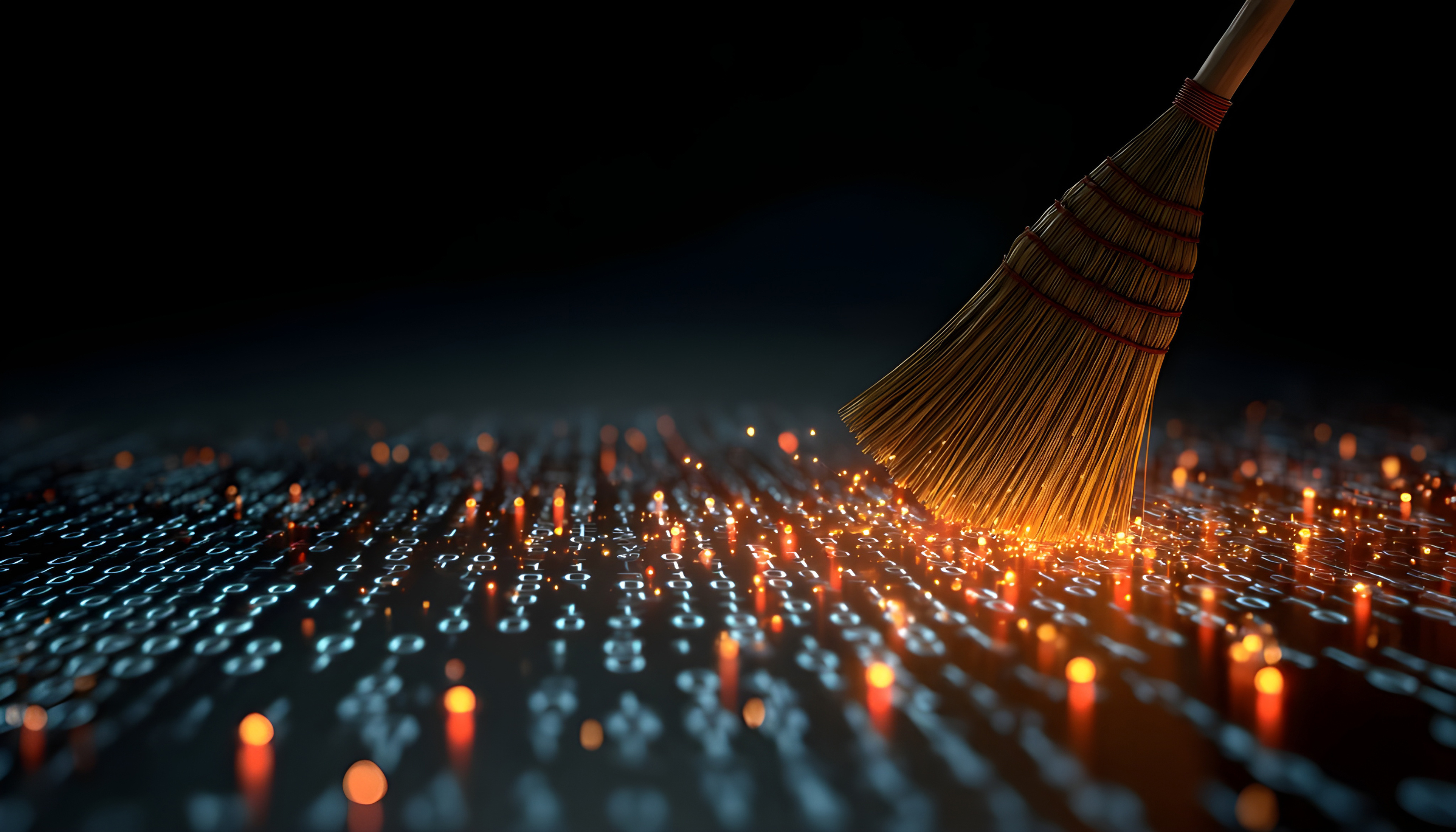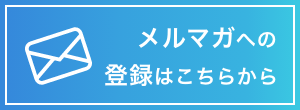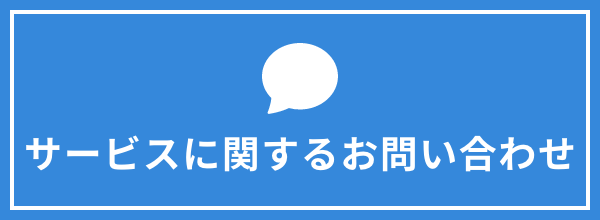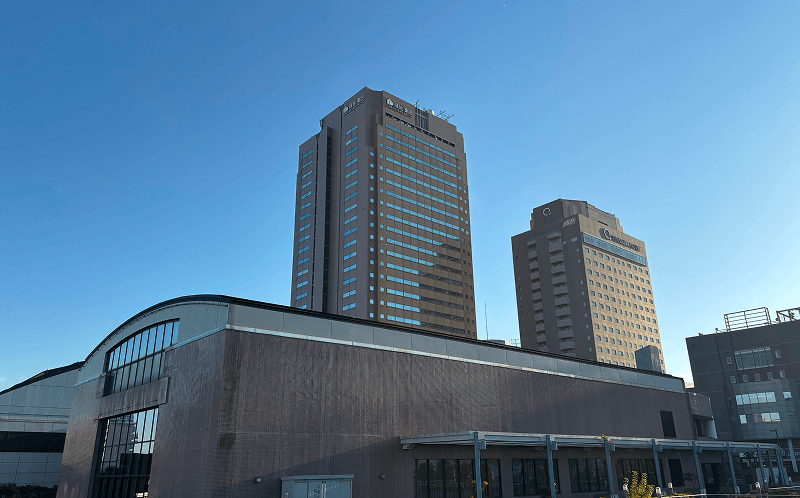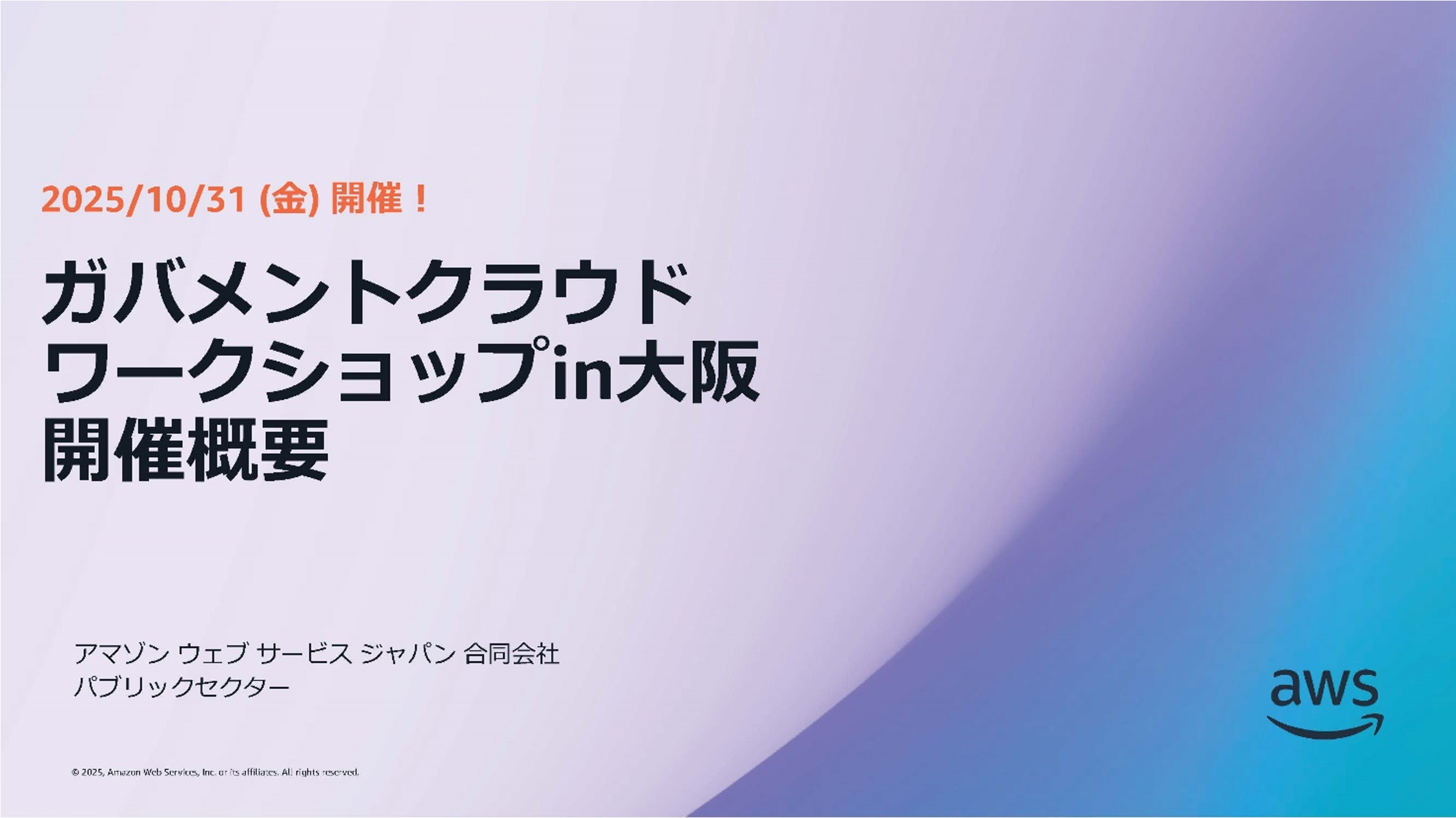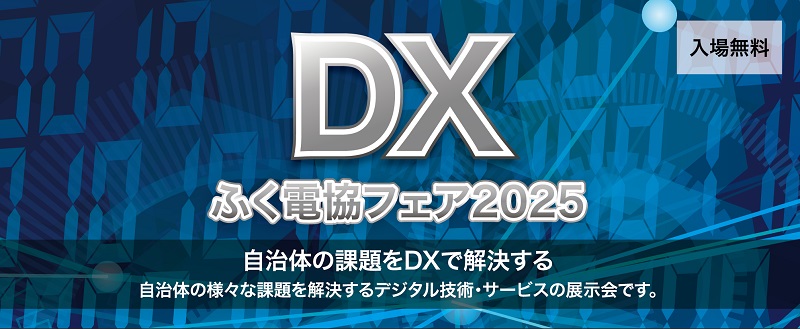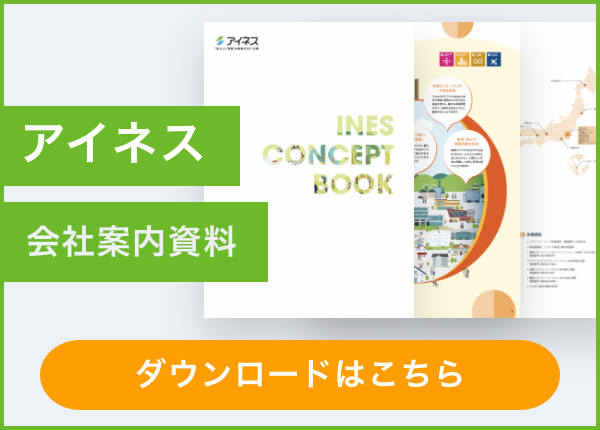- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- 小売業に求められる変革 今DXが必要な理由
公開日
更新日
小売業に求められる変革 今DXが必要な理由

業界を問わず、デジタルトランスフォーメーション(DX)が浸透し始めています。経済産業省もたびたびレポートを発表し、企業のDXを推奨しています。
小売業においても、先進的な企業はすでに取り組みを成功させ、新たな購買体験を生み出しています。DXによって変革させられるのは、購買体験ばかりではありません。DXに成功すれば、顧客満足度向上や従業員満足度の向上につなげることができるのです。
本コラムでは、小売業が現状で抱える課題やDXの必要性、小売業がDXに取り組むメリット、事例などをご紹介いたします。
【関連記事】
テクノロジーの進歩がビジネスの在り方を大きく変える!顧客体験を向上させるデジタルディスラプションとは
小売業が抱える課題点とDXの必要性
まずは、現状において起きている3つの変化をおさらいしておきましょう。ここから、小売業が抱える課題が見えてきます。
時代特性の変化(モノが売れない、売れにくい時代)
戦後、モノの不足している状態から高度成長期を迎え、あらゆる市場が拡大しました。バブル崩壊を経て、昭和から平成へと元号が変わり、各家庭には必要なモノがほとんど行き渡るようになります。
そこで、各メーカーは競合製品との差別化を図ろうと、さまざまなバリエーションをつけて売り出しました。その結果、消費者は自分の好みに合ったモノを選択できる状態を当たり前に享受するようになりましたが、高度成長期ほどモノが売れる時代は期待できません。
さらに、デフレや品質の向上などの影響で、安く良いモノが手に入り、長く使えるようになったこともあり、モノが売れない、売れにくい時代へと時代の特性は変化しています。
購買行動の変化(店舗のショールーム化、ECの台頭)
インターネットやスマートフォンなどが普及するまでは、店舗へ足を運んで商品を見て選び、購入するというのが一般的な購買行動でした。また、商品の選び方には、テレビなどマスメディアの広告や友人知人からの口コミが大きな影響を持っていました。
現在では、パソコンやインターネット、スマートフォンなどが普及し、ECでの購買も当たり前になりました。また、WebサイトやSNS上で商品の口コミをチェックし、購入判断の参考にする人も増えています。
その結果、店舗は実際の商品を手に取って確認するためのショールームと化し、店舗で確認して購買を決めてから、店舗価格よりも低価で販売されているECサイトを探して購入するというケースも増えています。
このことから、「店舗に来客はあっても売上には結びつかない」という現象が起きるようになってしまいました。
モノの価値の変化(サブスクや使い放題サービスの台頭)
これまで消費者は、モノを所有することに価値を求めて購買行動を行ってきました。
しかし、モノが行き渡り、また大抵のモノが手に入るようになった現在では、「モノ」よりも「体験」が求められるようになっています。
その結果、サブスクリプションモデルなど定額で使い放題のサービスが台頭しました。
これらの変化はいずれも、既存の小売業からすれば脅威でしょう。これまでのやり方に固執せず、新たな環境に適応して、変革していく必要があります。
そこで、DXが求められているのです。
小売業がDXに取り組むメリット
小売業がDXに取り組むことで、上記のような変化に対応できるようになります。
本章では、小売業がDXに取り組むメリットをまた別の角度から捉え直してみます。
顧客体験(CX)の向上
前章でもお伝えしたように、消費者が求めるのはモノからコトへと変化しているため、プロモーションから購入、アフターサービスに至るまで、購買を通して顧客にどれだけ新鮮で心地よい体験をしてもらえるかが競合他社との差別化のカギとなります。
たとえば、レジでの待ち時間をなくしたり、家にいながら商品を試せたり、どの店舗に欲しい商品の在庫があるのかを把握できたり、などが一例です。キャッシュレス化も顧客体験向上のための要素の一つで、顧客は現金を持ち歩かなくても買い物を楽しむことができ、面倒な会計の際のお釣りのやり取りをせずに済むようになります。
こうした顧客体験の向上は、最終的には「顧客満足度の向上」へとつながっていきます。
DXに取り組むことによって顧客体験を根本的に変革させることで、顧客は新鮮な体験や快適な買い物を楽しめるようになり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
コスト削減
DXによって、これまで当たり前にかかっていたコストを削減することも可能です。
たとえば、RPAなどのデジタル活用により、人件費を削減することができます。
店舗運営ではこれまで、万引き防止のために警備員を巡回させるなどの対応が必要でした。そこへ、AIが搭載されたスマートカメラを導入することで、不審な動きをする人物を認識してアラートを出すようにすれば、スタッフが警戒することで万引きを防止できるようになります。
業務効率化の実現
最新のデジタルテクノロジーを導入することにより、業務フローが再構築され、業務の効率化を実現できます。そもそも当初から業務効率化を目的としてDXに取り組む企業も少なくないでしょう。
デジタルの導入により、本部からスタッフへ、またスタッフ間での情報伝達がスムーズで正確なものになりスピードアップも実現可能ですし、棚卸し・検品といった作業も効率化できます。さらには、スタッフ研修にかかる手間も削減できます。ほかにも、データ管理の簡略化や勤怠管理の効率化など、あらゆる業務でデジタル化による業務効率化の可能性があります。
こうした業務効率化は、コスト削減に直結するばかりでなく、従業員満足度の向上にも貢献します。なぜなら、業務フローの変更やデジタル技術の活用によって従業員の負担を減らすことができるからです。たとえば、キャッシュレス化を導入した場合、店舗スタッフがレジ締め作業にさく時間と労力を削減できるといった具合です。
DXへの取り組みは、従業員の自社に対する高評価にもつながるでしょう。先進的な取り組みを行い、ビジネス環境の変化に対応していることで、将来性を実感する従業員も出てくるはずです。
小売業が目指すべきOMOとは
小売業がDXを推進する上で知っておきたいのが「OMO」という概念です。
OMOとは?
OMO(Online Merges Offline/オンラインとオフラインの融合)とは、今後、すべてのオフラインがオンライン化されることを見据え、オンライン環境をベースにオフラインと融合させるという考え方です。商品・サービスからその提供方法、プロモーションからアフターサービスまで、あらゆるフェーズで今後、OMOが広がっていくでしょう。
提唱者は、中国で次世代ハイテク企業を育てることを目的にベンチャーキャピタル「シノベーション・ベンチャーズ」を立ち上げた李 開復(リー・カイフー)氏。グーグル中国法人の社長も務めた人物です。
以前から、O2Oやオムニチャネルという概念はありましたが、これらはあくまでもオフラインを起点とした考え方でした。一方、OMOはオンラインを起点としており、O2Oやオムニチャネルの進化形であるともいえます。
OMOとDXの関係
OMOとDXに直接的な関係性はありませんが、ある意味においてはDXがOMOを内包しているともいえます。すでにOMOに取り組んでいる企業にとっては「OMO=DX」にはなり得ませんが、O2Oやオムニチャネルに取り組んでいた企業がOMOに取り組めばDXですし、O2Oやオムニチャネルにも未着手の企業がこれらに取り組めば、それも立派なDXです。
DXが求められるようになった外的環境を鑑みると、より先進的な取り組みを実施しなければ競争力は低下していくでしょう。しかし、一足飛びにデジタル化を進めることは難しいため、自社が取り組めるところからまず行動するというのも賢明な選択だといえます。
小売業のDX事例
最後に、小売業界企業様に参考になるような先進企業のDX取り組み事例をご紹介します。
Amazon Go
OMOの先駆けともいえるのが、Amazon.comが2016年から展開している「Amazon Go」です。Amazon Goは、レジで並ばずに買い物ができるという新形態の小売店です。日本では「無人コンビニ」と紹介されることが多いですが、レジにスタッフがいないだけで実際には店舗で多くの従業員が働いています。
来店客は、AmazonのアカウントとAmazon Goのスマホアプリで、ゲートにQRコードを読ませて入店し、持参したエコバッグなどに棚から欲しい商品を入れて買い物をします。欲しい物を選び終わったら、再びゲートでスマホのQRコードを読ませて退店すると、数分後にアプリにレシートが届きます。
決済は、事前に登録しておいたクレジットカードから自動的に支払われるようになっています。ただ、クレジットカードを所有していない低所得者向けに一部店舗で現金決済も行われています。
来店客は、買い物の際に最もストレスの大きい「レジに並んで会計をする」という体験をせずに済みます。Amazon Goが掲げている「Just Walk Out(退出するだけ)」の言葉通り、欲しい物を選んで外に出るだけです。
この顧客体験を実現するために、店舗側では商品棚にセンサーやマイクを、天井にカメラを設置して解析することで、どの来店客が何を何個購入したかを正確に判定しています。
フーマー・フレッシュ(盒馬鮮生)
OMO先進国である中国の事例です。
B2Bのオンライン・マーケットからスタートしてECサイト「タオバオ(淘宝網)」や、電子マネー「アリペイ(支付宝)」などを展開するアリババグループが2016年からから出店しているスーパーマーケットが「フーマー・フレッシュ(盒馬鮮生)」です。
フーマー・フレッシュでは、店内に巨大な水槽が設置されており、その中には魚が泳いでいて、一種のエンターテインメントになっているといいます。さらに、その魚介類をその場で好きな調理法で調理してくれるサービスもあり、調理後は配送してもらうこともできれば、イートインスペースで食べることもできます。
決済方法も従来とは異なるセルフレジで、来店客は自身でバーコードリーダーを使って商品をスキャンし、最後にアプリに表示されるQRコードをスキャンして完了です。また、数は少ないものの、有人レジによる現金決済にも対応しています。
同社の創業者であるジャック・マー(馬雲)氏は「ニューリテール(新小売)」を提唱しています。ニューリテールとは、モバイルインターネットとデータテクノロジーを用いることで、小売業のDXを実現し、オンラインとオフラインを融合させた新しい消費体験を提供することだといいます。
フーマー・フレッシュでは、これを具現化しており、オンラインの利便性とオフラインでの買い物の楽しさの両方を提供しています。
三越伊勢丹ホールディングス
最後に、日本のOMO事例をご紹介します。
創業から340年以上の歴史を持つ三越伊勢丹ホールディングスでは、DXを通して「IT・店舗・人の力を活用した新時代の百貨店(プラットフォーマー)」を目指しています。
大きな柱は2つあり、1つは百貨店事業のDX、もう1つは新規事業の創出だといいます。
前者の具体的な取り組みとしては、たとえば、ECでは当たり前になりつつある、購買履歴や閲覧履歴からのリコメンド機能をリアルでも実現することや、靴3D足型計測機による顧客ごとの足サイズのデータ化と、靴のマッチングサービス「YourFIT365(ユアフィットサンロクゴ)」の提供など。
後者の取り組みとしては、高品質なカスタムオーダーのスーツやシャツを作ることができる「Hi TAILOR(ハイ・テーラー)」が挙げられます。これは、AIを搭載した自動採寸システムで、専用サイトにアクセスして生地やデザインを選んだ後、自分の全身を撮影するとAIが各部位の採寸を自動で行ってくれ、最短3週間で商品が自宅に届けられるというもの。また、採寸したデータは保存され、次回以降の注文では採寸を省略することもできるといいます。
同サイト上から三越伊勢丹のスタイリストに相談することもできるようになっており、単にデジタル技術だけでなく、もともと培ってきたノウハウや人的リソースをも活用している好例です。
まとめ
現代は、モノが売れない時代であり、小売業は生き残りをかけて対策を講じる必要があります。
DXに取り組んで顧客に新たな価値を提供することで、生き残るばかりか成長拡大できる可能性も開けてきます。
これまでに蓄積してきた自社の強みを活かしつつ、最新のデジタルテクノロジーの力を使って業務プロセスやサービスを変革していきませんか?
小売業のDXについては、今後もお役に立てる記事の掲載を予定していますので、ご期待ください。
アイネスでも、デジタルトランスフォーメーション活用に向けた、ITサービスを提供しております。また、流通・小売業様向けに第3世代基幹システム「REAL MD Series」をご提供しています。小売業の総合的な支援はアイネスにお任せください。
【関連サービス】小売業向け第三世代型基幹MDシステム「REAL MD Series」
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。
ITでお悩みのご担当者様へ
弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。

関連記事