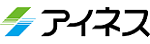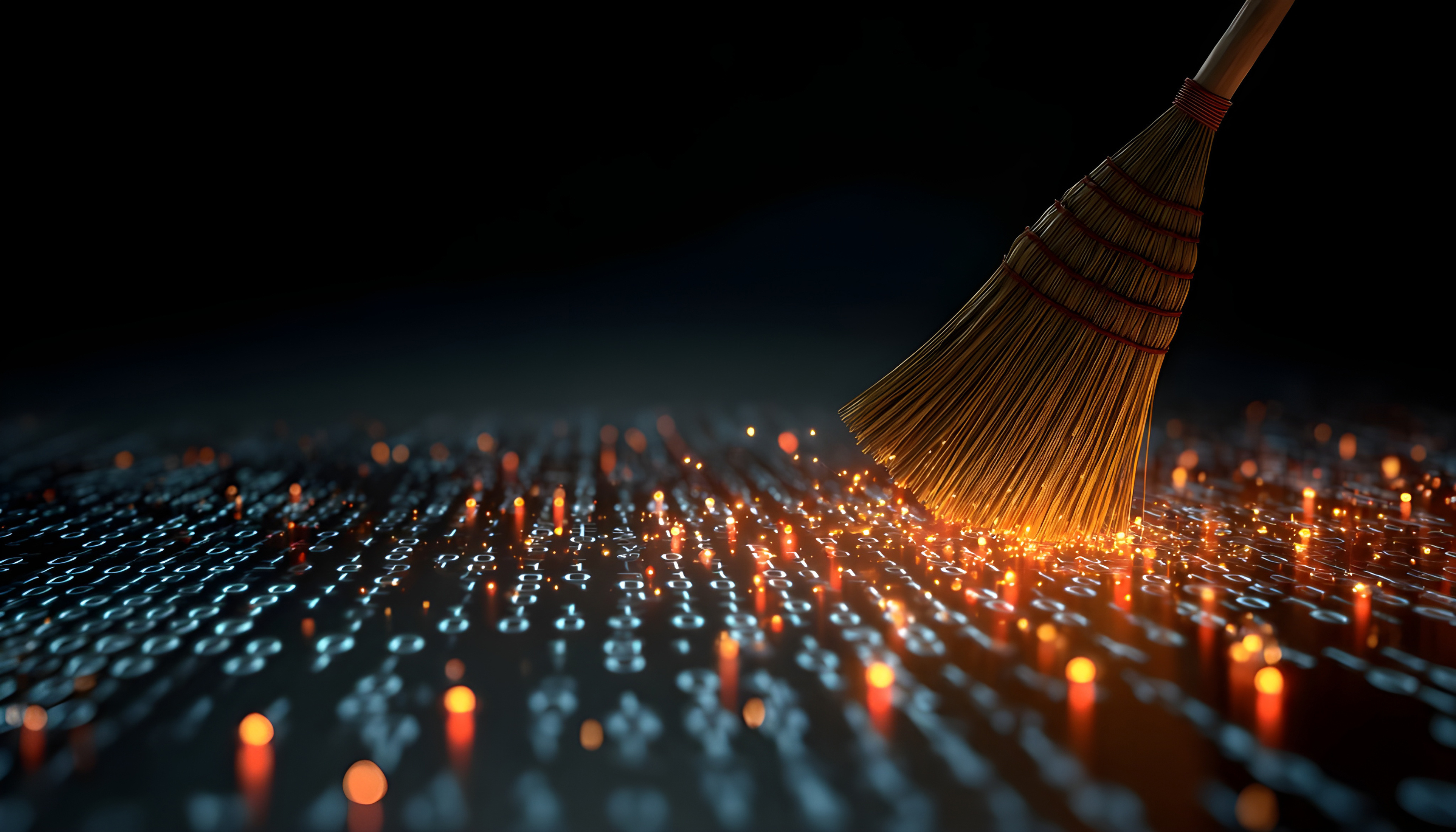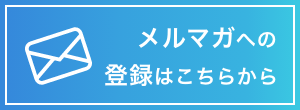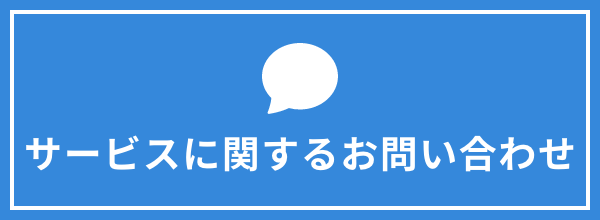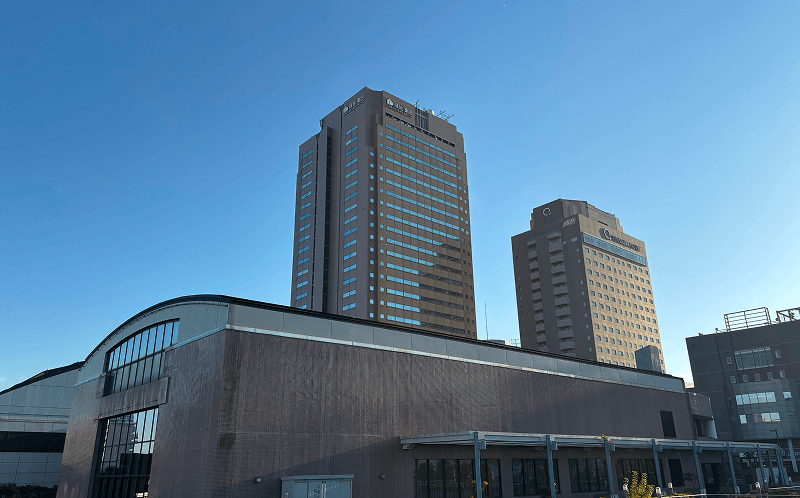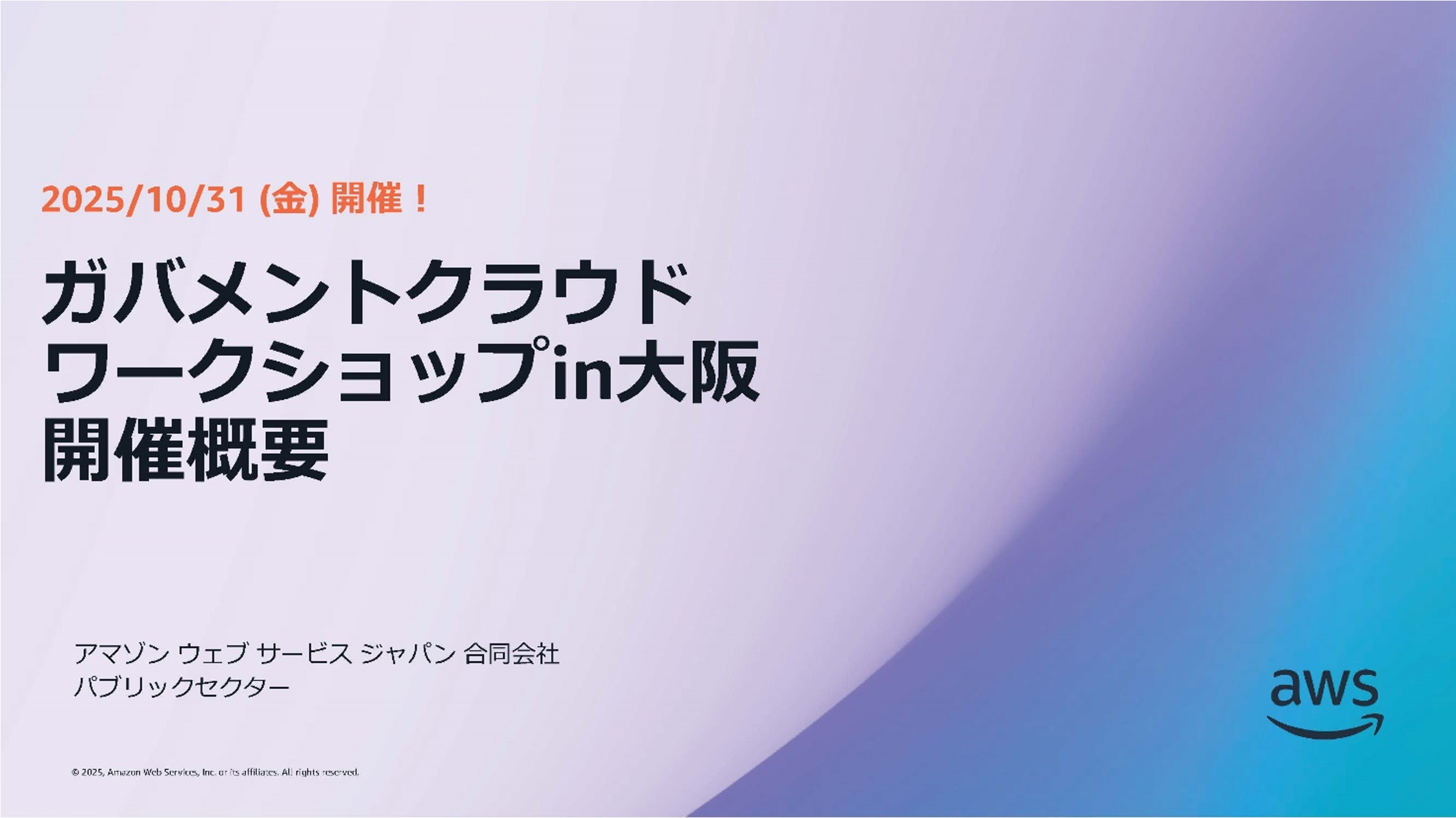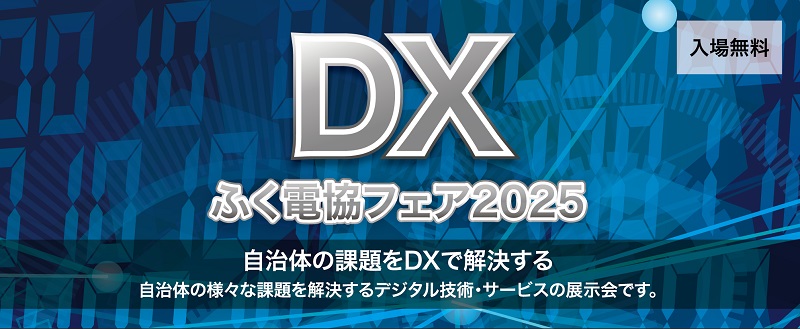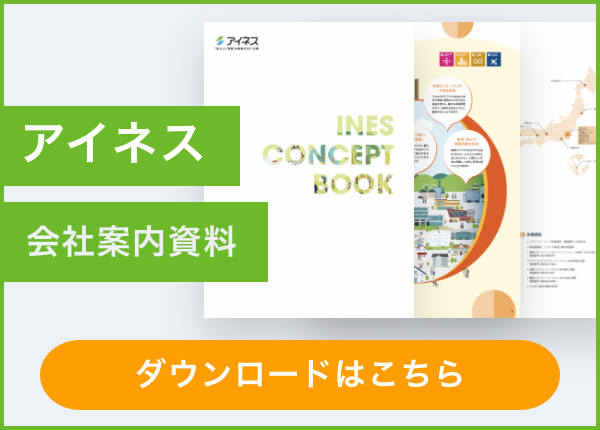- たぷるとぽちっと|ITに関するお役立ち情報サイト
- ITお役立ち情報
- インボイス制度とは?2023年10月の開始前に知っておきたい対策内容
公開日
更新日
インボイス制度とは?2023年10月の開始前に知っておきたい対策内容

2023年10月1日より、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」がスタートします。
すでに、課税事業者として登録が済んでおり、請求書のフォーマットも準備できているところもあるでしょう。
一方で、そもそもインボイス制度がどのようなものか、あまり理解できていない企業様もあるのではないでしょうか?
今回は、約1年後に開始が迫ったインボイス制度について、その目的や影響範囲、対策方法をご紹介いたします。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことで、所定の記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)を発行または保存することで、消費税の仕入額控除を受けられる制度のことです。
適格請求書の利用
請求書や納品書への具体的な記載要件は、次の8点です。
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 登録番号(課税事業者のみ)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
上記のうち、上から5点は、現行の請求書(区分記載請求書)の記載項目で、下から3点がインボイス制度で新たに追加される項目です。
課税事業者としての登録
また、インボイス制度を導入する事業者は、あらかじめ課税事業者として登録する必要があり、すでに令和3(2021)年10月1日から登録を受け付けており、令和5(2023)年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。
なお、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、すべての事業者が課税事業者として登録することを前提に作られた制度ですが、対応しなかったからといって罰則があるわけではありません。
ただ、未対応の場合、課税事業者から購入した際に、より多くの消費税を支払わなければならなくなるため、特別な理由がない限りは、全事業者が課税事業者として登録と、請求書フォーマットの対応を行うことをおすすめいたします。
請求書を送る側も、受け取る側も、請求書や写しの保存義務がある
もう1点、請求書の保存義務も追加されています。
これまでは、請求書を受け取る側のみに保存義務がありました。インボイス制度開始後は、送る側も写しを保存しておかなければなりません。
ただし、自動販売機でのジュースの購入など、請求書等の交付を受けることが難しいケースでは、適格請求書発行事業者の義務が免除されるものがあります。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的には、大きく次の2点があります。
正しい消費税の納税額を算出するため
「「適格請求書等保存方式」の適用」で詳しくご紹介しますが、2019年10月から消費税率が10%に引き上げられた一方で、飲食料などは8%に据え置かれる軽減税率がスタートしたことで、複数の税率が混在するようになりました。2つの税率が混在するようになった軽減税率(複数税率)においても、正しい消費税の納税額を算出するために、インボイス制度が導入されます。
インボイス制度開始までの前提措置として、2019年10月から「区分記載請求書等保存方式」が導入されていました。
区分記載請求書等保存方式は、インボイス制度導入までの経過措置だったため、インボイス制度の導入に伴い、「区分記載請求書」は廃止されることになります。
ただし、経過措置として、2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日までは仕入税額相当額の50%の控除が認められています。
益税を解消するため
事業者が消費税を納税する際の基本的な仕組みは、課税対象となる取引で受け取った消費税と、支払った消費税の差額を納税するというものです。
ただ、中小・小規模事業者向けには特例が用意されています。年間の売上が5,000万以下の事業者は「簡易課税制度」が、同様に1,000万以下の事業者は「免税事業者」が選択できるというもので、これらを選択した場合、実際に支払う税金額よりも多く、消費税を受け取るケースが出てきます。この差額分は、そのまま該当事業者の収益となるため「益税」とよばれて問題視されています。
インボイス制度の導入で簡易課税制度は廃止されるため、これまで簡易課税制度を利用してきた事業者は、課税事業者の登録を行う必要があり、益税は解消されます。
一方、免税事業者は、課税事業者の登録を行うか、それとも免税事業者にとどまるのかを決める必要があります。その際、取引先が個人、つまり一般消費者であれば、大きな影響は出ない可能性が高いです。しかし、取引先が企業のフリーランスの場合は、課税事業者の登録をした方が良いため、益税は受け取れなくなります。
インボイス制度による変化
インボイス制度の導入によって、2023年10月1日からどのような変化があるのでしょうか?
「適格請求書等保存方式」の適用
2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」つまりインボイス制度が適用されるようになります。
繰り返しになりますが、従来の請求書の項目に、次の3つの項目が追加されます。
- 課税事業者の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
「区分記載請求書」との違い
なかには、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」を「区分記載請求書等保存方式」と混同している方もいらっしゃるかもしれません。
「区分記載請求書等保存方式」とは、2019年10月から導入された請求書のルールで、2019年10月から消費税率が10%に引き上げられた一方、飲食料などは8%に据え置かれ、複数税率(軽減税率)がスタートしたことから、請求書の記載および経理の方式が変更されたものです。
従来の請求書の項目に、軽減税率の対象品目である旨と、税率ごとに合計した対価の額(税込)が追加されました。
インボイス制度では、「区分記載請求書」に加え、さらに課税事業者の登録番号と、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3点を記載する必要があります。
インボイス制度による影響範囲
上でも触れましたが、インボイス制度の影響を受けるのは、課税事業者と、課税事業者と取引する免税事業者です。
まず、課税事業者には、インボイス(適格請求書)の発行が義務付けられます。そして、インボイス(適格請求書)を発行するには、前述の通り、適格請求書発行事業者となるための申請・登録が必要になります。その上で、取引先から求められたら適格請求書を発行し、写しを保存しておく必要があります。
一方、免税事業者は、課税事業者と取引があってもインボイスを交付することができません。
このため、免税事業者から購入した課税事業者は、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。このことから、免税事業者との取引を拒否する課税事業者が表れる可能性があります。
小売業においては、顧客の多くが個人である場合は、免税事業者のままでも大きな影響は出ない可能性があります。しかし、顧客に企業など法人が含まれる場合は、1年間の課税売上高が1,000万円未満であっても、課税事業者の登録を行った方が良いでしょう。
もちろん、1年間の課税売上高が1,000万円以上の小売業であれば、請求書のフォーマット変更を含め、早目に対応を行うことをおすすめいたします。
インボイス制度への対策方法
「適格請求書の利用」でもご紹介しましたが、2023年10月1日以降は、以下の項目をもれなく記載した適格請求書を発行する必要があります。
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 登録番号(課税事業者のみ)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
さらに、書類の受け取り主はもちろん、送り主にも写しを保存する義務が発生します。
このようなインボイス制度への対応を紙ベースで行っていると、作業や保管場所が増加して非効率的です。
EUや韓国など、海外ではすでに電子インボイスの導入が進んでいます。日本でも将来的には、すべての請求書や納品書が電子化されることになるでしょう。実際に2021年9月、デジタル庁の平井大臣(当時)は、海外ですでに普及している国際規格「Peppol(ペポル)」の日本版が、Peppolの管理団体「Open Peppol」のWebサイトに公開されたことを公表しました。
こうした流れを見ると、インボイス制度を機に、請求書や納品書の電子化にも取り組むことで、先手を打つことができるといえそうです。
まとめ
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始される、請求書や納品書に関する新しいルールです。現状の「区分記載請求書」に加え、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3点が記載項目となります。また、受け取り手だけでなく、送り手にも保存義務が生じます。
適格請求書を発行するためには、課税事業者の登録が必要で、2021年10月1日から登録を受け付けているため、インボイス制度への対応を予定している事業者様は、早目に登録を済ませておきましょう。
また、新たな請求書のフォーマットへの対応も必要になります。まだ紙ベースで請求書や納品書を発行している事業者様は、将来的な電子インボイスへの切り替えも見越して、このタイミングで電子化へも対応しておくと良いでしょう。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。ITでお悩みのご担当者様へ
弊社は、情報サービスのプロフェッショナルとして、システムの企画・コンサルティングから開発、稼働後の運用・保守、評価までの一貫したサービスと公共、金融、産業分野などお客様のビジネスを支える専門性の高いソリューションをご提供しています。お気軽にご相談ください。

関連記事